顕微鏡をのぞく合間に『消閑雑記』という本を拾い読みしていたら、おもしろい話がのっていた。
江戸時代のはじめ、因幡国鹿野(現在の鳥取市鹿野町)に「崑崙坊」と呼ばれる黒人の大男がいたというのである。
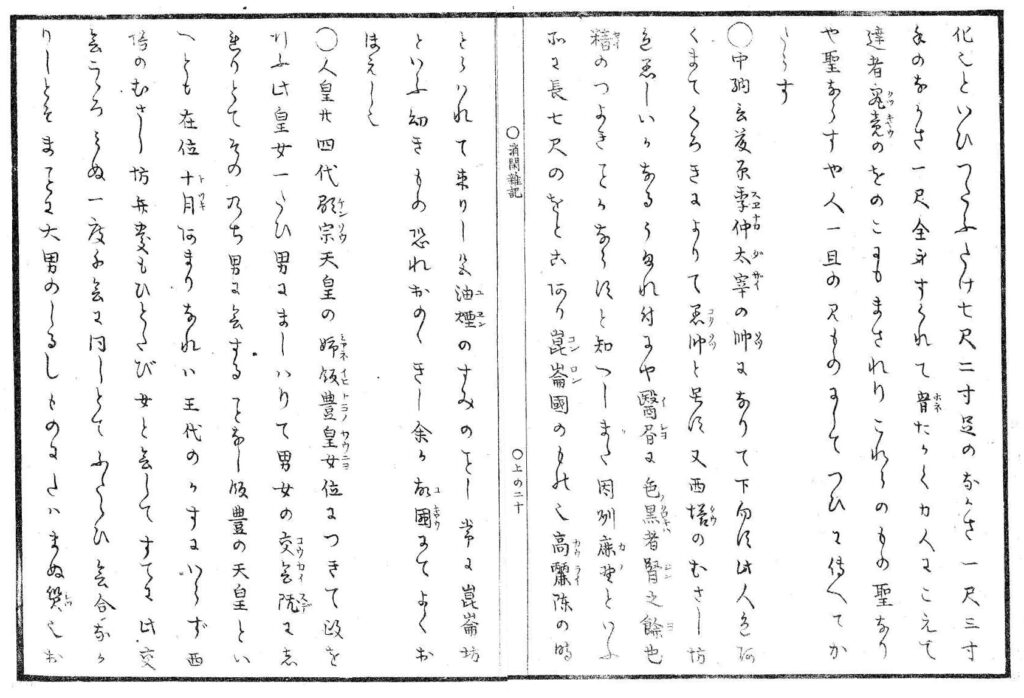
因州鹿野といふ所に長七尺のをとこあり。崑崙國の者なり。高麗陣の時とらはれて來りし。色油煙のすみのごとし。常に崑崙坊といふ。幼きもの恐れおのヽきし。余が故國にてよくおぼえし。
消閑雑記上巻「季仲のこと 付くろん坊」・引用者が句読点および濁点を補った
『消閑雑記』は岡西惟中の作。
惟中は江戸初期の俳人で西山宗因に師事した。彼の「俳諧とはなんぞ。荘周がいへらく滑稽なり。とはなんぞ。是なるを非として,非なるを是とし,実を虚にし,虚を実になせる一時の寓言ならんかし」なんかは聞いたことがある人が多いだろう。なお一尺はだいたい30センチメートルなので、崑崙坊は身の丈2メートルを超える大男だったということになる。まあ「長七尺」は大男をあらわす慣用句なので真に受ける必要はない。
興味を引かれたのは、崑崙坊は文禄・慶長の役で捕虜となって日本に連れてこられたという記述である。当時の鹿野城主は亀井茲矩である。茲矩は泗川船滄、弥勒島唐浦で李舜臣に敗れたが(『乱中日記』)、上陸して東古都城、蘇川城、機張城と転戦し朝鮮軍を大いに破るなど活躍した。崑崙坊はおそらく朝鮮軍の水夫かなにかで敗戦のさなか俘虜となったのだろう。
いわゆる戦国時代、ポルトガル人によるアフリカや東南アジア人の奴隷売買が盛んであったことはよく知られたことである。たとえばルイス・フロイス『日本史』に沖田畷の戦いの際に龍造寺側で砲撃を担当し戦列を維持した黒人傭兵がいたという記述がある。
ところでその場には砲手がいなかったので、一人のアフリカのカフル人が弾丸を込め、一人のマラバル人が点火していた。そうした厄介な操作にもかかわらず砲は見事な協力のもと発射を始めた。何分にも敵兵は大群であったから弾丸が当たり損ねることがなく(以下略)
ルイス・フロイス著、松田毅一・川崎桃太訳『日本史』第53章
「カフル人」はアフリカ東海岸モザンビーク出身を指し、「マラバル人」はおそらくインド人である。
彼の呼び名「崑崙坊」は「崑崙奴」「黒坊」と同じく単に「色が黒い人」というだけで、彼がアフリカ出身かどうかまではわからない。『西遊旅譚』に「崑崙ぬハ彼國の詞にてハ スワルトヨンゴと呼 ジャガタラの人なり」、『甲子夜話』に「其近『ジヤワ』『シアムロ』辺ヨリ來ル黒坊ナドノ」とあるように、東南アジア出身ということも十分ありえることである。今となっては崑崙坊がどこの出身かはわからないが、欧米人による売買の結果日本に漂着したという点は間違いあるまい。
彼――崑崙坊はどうなったのだろうか。
崑崙坊についておそらく唯一の記述をした惟中は寛永十六年(1639年)、因州鹿野の産である。はや文禄・慶長の役は四十年も昔のことになっていた。「子供たちは崑崙坊を見ては怯えていた」と言うように惟中が物心ついたころ崑崙坊がいたとすれば、当時既に彼は老境に差しかかっていたはずである。寛永年間には亀井茲矩はすでに亡く、元和年間に亀井氏は津和野に転封となり、鳥取には代わって池田氏が入った。そして、海禁策により一介の囚人が帰国するすべはなかった。崑崙坊はおそらく極東の異国の地で生を終えたのだろう。
ただ、私は、彼が幽囚として飢困憂悶の裡に死んだと思いたくない。
私はひとりひそかに夢想する――彼が自足の生活をしつつ心穏やかに生活する姿を――これは全く故ないことではないのだ。『因幡民談記』には、崑崙坊と同じように鳥取に連行された捕虜についてこのような記載がある。当時の鳥取城主、宮部継潤は大勢の朝鮮人捕虜を連行したが*、どうも言葉の通じない彼等は使いみちが限られたらしく、城下に放置したものの彼等は困窮している様子であった。そこで因幡銀山に米を運ぶ役目を与えたところ、彼等は外で安い米を仕入れては鉱山内で高く売りさばくようになった。鉱山内は人の出入りが厳重に制限されていたため、米が高値で取引されたのである。朝鮮人俘虜は毎日休まず米を運んだので次第に豊かになり、なかには城下に定住する大商人になるものまであらわれたという。
* 正確には渡海した子・長房が連れ帰ったもの
崑崙坊を捕えた亀井茲矩は琉球守を名乗るなど南方に強い興味を抱いていた。彼は三度にわたり朱印船を派遣したが、その二回目と三回目(慶長十四・十五年)の行先はシャムであり、マレー半島にあったパタニ王国も含まれていた。もしかすると、その海外交渉のなかで崑崙坊は現地の言葉や風俗を知る者として朱印船に乗りこんでいた、なんてことがあったかもしれない。
私はひとりさらに夢想する――彼は朱印船に乗って故郷を再訪することができたのだと。そして、いくらか仕入れた品を金に換えて田畑を買い、日本で自足の生活をおくったのだと――むろんそれを裏づける史料などありはしない。これは私の迷妄である。ただ、そういうことにしておこうではないか。ある日の早朝、雀が喧しく鳴くなか、彼は鋤をかついで畑へ出てゆく。木陰から恐る恐るこちらを覗う惟中らに柔らかく微笑みつつ、彼は故郷の歌を口ずさみながら歩いてゆく。その瞬間からあとのことは、私はなにも知らない。
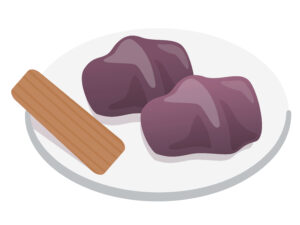




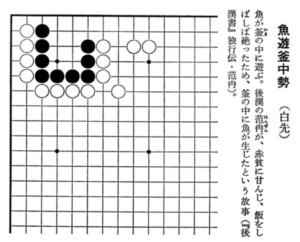
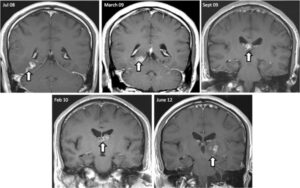

※コメントは最大500文字、5回まで送信できます