こどものころ、よく味噌汁をごはんにかけて食べていた。
そのたびに前で食事をしていた父が「ねこまんまだな」と渋い顔をしたのを憶えている。「どうもこれは不調法な行いらしい」といつしかやめてしまったのだが、今でも内心腑に落ちない思いが残っている。
またある日、クリームシチューが食卓にのぼったことがあった。私はジャガイモやらニンジンやらをそれぞれ味わった後、おもむろに茶碗を傾けてごはんを投じたのだが、この時も父はギョッとした顔をした。私は「ドリアやカレーと同じではないか」と抵抗を試みたが、父は黙って首を振っただけであった。これもいつしか……というようなことはなく、今でも家でシチューを作ることがあれば普通にご飯を投じている。家の外ではお節介者の珍奇の目に晒されるのを厭うてやらないだけである。
父子と汁かけ飯というと、1650年代に成立した『武者物語』の北条氏康・氏政父子の逸話が有名である。
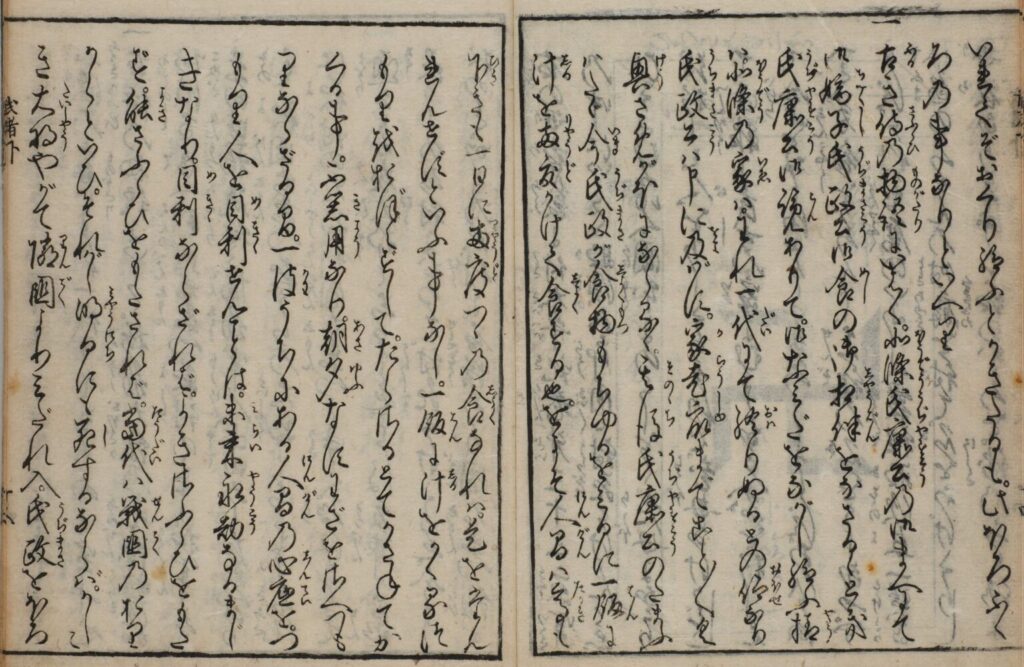
そして北条家は氏政の代で滅んだのであった――という創作である。なお正確には、小田原征伐で後北条氏が滅んだのは氏政の子、氏直の代である。
ここで重要なのは、氏康は飯に汁をかけたことは別に咎めていない点である。これは当然のことで、当時の武家故実書にも
武家にては必ず飯碗に汁をかけ候
『宗吾大雙紙』飯に汁をかくる事
一 本膳のさいを右の手にてのけて、扨食をわけて、しやうじんの汁をかけて、大汁ひや汁同前、但時の景物共にて、魚類共あらばそれをかけべし
『伊勢守貞宗朝臣記』(『古事類苑』より)
とある。武家だけではなく、鎌倉末期の『世俗立要集』にも
後鳥羽御宇ノ水無瀬殿ニテ卿相雲客ノ中ニテ供御ノ参リシニ、仰セニイハク。飯ヲ汁ニツケズ、先ニ汁ノミヲ食ヒ、汁ヲススル事ハ、マサナキ事也。
『世俗立要集』(引用者が句読点を補った)
とあるように、古くから身分の高い人でも普通に飯に汁をかけて食べていたことがわかる。
『醒睡笑』には「継母の盛りたる飯は富士の山 汁を掛くれば浮島ヶ原」なんていう狂歌がある。富士山麓の浮島ヶ原は当時低湿地帯で、雨が降れば容易に沼地と化した。これは「継母がよそう飯は一見富士山のように大盛りだが、汁をかけると(中が空なので)たちまち崩れてぺちゃんこになってしまう」という継子いじめの話である。
一方で庶民はどうだったかはよく分からないのだが、「汁かけ飯」を禁忌とした話は見あたらないようである。
ただ、赤飯に関しては「小豆飯に汁を掛けて食ふと婚禮や葬儀の日に雨が降る」という言い伝えが日本のあちこちにある。私が調べた限り陸前登米郡、武蔵入間郡、三河額田郡、備前上道郡、また尾張や伊勢でこの口碑が見られる。確かに赤飯に汁をかけてしまってはその風味を損なうこと夥しいので、これを戒めるのはしかたないかもしれぬ。むろん好きな人はすればよいし、すこし塩気をきかせた澄ましならば案外と合うかもしれない。
ちなみに小笠原流礼法伝書では「粥に汁をかけるな」という条がある。これは「粥にした意味がないだろ(かゆのわけをせぬものなり)」とまあ当然のことである。
さて普通の飯に汁をかける話に戻ると、いつ頃からかわからないが、汁のかけかたにもいろいろお作法ができたらしい。
ひとつは「目上の人が汁をかけるまで待たなければならない」というものである。
食にしる先はかけぬと思ふべし上客かけば我もかけべし
『常の食喰樣曳歌』(『古事類苑』より)上客じやうきやく飯いひに羮しるをかけば、相伴しやうばんの人も、各をの/\飯いひに汁しるをかくべし。
『食禮口訣』悔艸に貴人よりはやく汁などかけず、湯をのむとも見合て、はしを下におくべしなどいへり
『嬉遊笑覽』十上飮食(『古事類苑』より)飯に汁をかけ候事は、上客を見合する也、上客早く參り仕廻給はゞ、各早く喰終るべし、貴人汁をかけ給ふを見て、皆々汁をかくる也
『禮容筆粹』 七(『古事類苑』より)
どの汁をかけるかもまた決まっていた。かけるのは基本的に冷汁である。本膳につく本汁や実の入った汁をかけることはあまり推奨されなかった。
飯を喰ひおはらんとする時、二の羮あらば、二のしるをかけ、二汁なき時は、本汁をかけて、飯を喰ひつくすべし。
飯に躬物の汁をかけてくふこといやし。
『食禮口訣』一食に汁懸候事は、冷汁を懸候て能なり、但時宜によるべし、珍敷物などならば、本汁懸候ても不苦也
『躾方明記』四(『古事類苑』より)
また汁のかけ方にも細かい注文がつくようになった。
汁をかける時はあらかじめ飯を食べて減らしておき、飯が無くなった所に少しづつ汁をかけ、飯を崩しながら食べよ、というものである。当然ながら山盛り飯に汁を「だばあ」とかけてかき混ぜるなんてのは外道、ということになる。まあぐちゃぐちゃとかき混ぜるのを見苦しく思う気持は分からないでもない。
またそうやって食べてゆき、碗に飯が少し残った状態で食べ終わるのが良しとされた。飯碗についた米粒を汁で洗って箸で掻き落とし、全部食べたりするのもまた不調法者ということになるのである。
一 めしに汁かくる事 かきまぜずして、かたくつしニくらふべし、くいはつる時、白いゝを少殘して置なり、
『伊勢守貞孝朝臣相傳條々』五(『古事類苑』より)汁をかくるに節之事
たとへば椀中を三分一程にくひへらして、片はしに汁を卒度かけ、少づゝ箸を以て汁にひたして喰べし、たくさんなる飯に上から汁をかけ、箸にて拌かきまぜ、椀中をよごし、四五分ならではよごさゞる箸を一二寸もよごし、あまさへ飯粒なんどの付たるを、橫ぐわへにくわへて是をおとし、或ははしと箸とにてかすりおとしなどする體、誠に見苦し、小人などは汁をかけ給ふ事あしゝ
『禮容筆粹』 七(『古事類苑』より)飯に汁かけて喰い畢りて、一粒も残さず喰う事、昔はなき事なり。然りといえども、残りたるは、見てむさき者也。但し、若輩の人、残さず食すれば卑しき者也。
『分類草人木』
最後の『分類草人木』は戦国時代に成立した茶道書だが、「飯が残っているのは下品である」と言ったり「若輩者が一粒も残さず喰うのも卑しい行いだ」と腐したり、忙しいことである。結局何をしてもこの手の人間は文句をつけるのである。その点、益軒なんかは、上でも引いたようにコマゴマと註文をつけているのだが、「飯に汁をかけるのは、飯・汁を全部食べ、食事を出してくれた主人に報いるためである」「しかし必ず全て食べなければならないわけではない。そのときの腹具合もあるし、病氣でたくさん食べられないときもある。そういう時はしかたがないし、飯に汁をかけなくてもいい」と柔軟な姿勢を示している。
汁かけ飯が日陰者に追いやられたのはいつからだろうか。
明治時代に西洋料理が入ってきてから徐々に貶められるようになったのではないか、と私は漠然と考えていたが、冒頭に挙げた「シチューかけごはん」(シチウ飯)なんかは普通に明治大正期の料理書に載っていたりする。よくわからないことである。誰かこの点について研究してくれないだろうか。
つらつら眺めてきたが、父と子と食事作法というと、私はいつも『カーブースの書』を思い出す。これはかつてカスピ海南岸を支配したイスラーム王朝、ズィヤール朝の第七代当主、カイ・カーウースがわが子に王たる心得を説いたものである。
その中で一章を割いて彼は息子に食事作法についてこまごまと注意を与えている。
曰く、食事は一日二回、朝はひとりで軽い食事をとり、午後は人を招いて共に食事をとるように。
曰く、食事は時間の余裕をもってゆっくり食べるように。
曰く、食事はまず客人のものを並べるように。
曰く、食事中気難しい態度を取ったり、口論をしてはならない。
そしてこのようなものもある――「知れ、息子よ。食事中に人と話をすることは大切で、イスラームのさだめである。しかし、頭を出して他人の食べ物をのぞき見てはならない」
彼が聞くところによると、ブワイフ朝の宰相サーヒブ・イスマーイール・ビン・アッバードが家來と共に食事をしていたとき、家來の食べ物に髪の毛がついているのに気づき「これこれ、食物から髪の毛を取りなさい」と言ったことがあった。すると、その家來は食事をおいてどこかへ行ってしまった。サーヒブが人をやって連れ戻させ「なぜ食事なかばで席を立ったのか」と尋ねたところ、家來は「私の食物についていた髪の毛を見るような人の食事を食べたくありません」と答えたので、彼はいたく恥じ入ったという。
サーヒブはただ親切心からそうしたのだろうが、それですら心ある人には忌まれたのである。カーウースはこの話を紹介しつつ「そなたは、まず、自分のことを気にかけなさい」と息子に訓戒を施している。
当時ズィヤール朝は一地方政権に過ぎず、常にセルジューク朝やガズナ朝に圧迫され、その命運は風前の灯火であった。カーウースはズィヤール朝の崩壊が近い事を予見し、息子がどのような運命を辿るにせよ、父として子に処世術と知識を授けようとしたのである。そう考えれば「他人の食べ物をのぞき見てはならない」も「猫まんまだな」もその時代に応じた指導なのかもしれない。今の世はとかく餘所見をする口さがない輩で充ち満ちているから、「猫まんまだな」はよい戒めと言えるだろう。まあ、なんでもいいのさ。父と子の間ならば。
カーウースの没後、彼の子ギーラーン・シャーがどうなったか確かなことはわからない
――ほどなくしてズィヤール朝が滅んだ、ということのほかは。
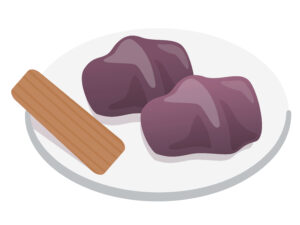




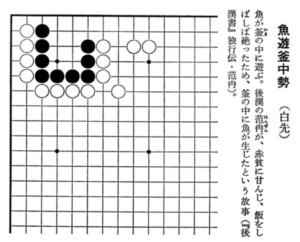
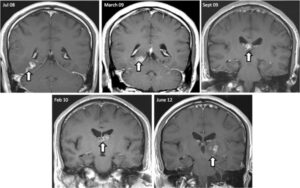

※コメントは最大500文字、5回まで送信できます