呼吸がとまった瞬間から、急にあたりに立ちこめていた濃密な霧が一時に晴れ渡ったような清々すがすがしい空気に私はつつまれていた。
十六の少女が生を終えたところから、この短篇ははじまる。
極貧に育った彼女は、家計のために働かされるうち、肺炎のため若くして命を落とした。そうして肉の軛から解きはなたれた彼女は、 澄み切った意識のなか、外の世界を静かに見つめる。
蜘蛛の巣は、裏の家のほの暗い庇の下に固着している。その庇の下に、雨を避けた小さな蜘蛛がひそかに身を憩うているのを、私の視覚ははっきりととらえることができた。新芽のように小気味よくふくらんだ華麗なその蜘蛛の腹部に、繊細な毛が無数に生え、その毛の尖端に細やかな水滴が白く光っているのさえ見てとることができた。
やがて一台の車が彼女を迎えにあらわれる――わずかな香奠料欲しさに、両親は彼女の死体を病院に売ったのだった。
彼女はまだ知らないが、研究用に新鮮な臓器を抜き取り、残った骸は医学生の解剖実習に付されるのである。当時はまだそれが合法であった。
病院職員と両親のやり取りを、まるで硝子の向こうの出来事であるかのように、彼女は淡々と描写する。生きては糊口を塗すために酷使され、死しては身を売られることに何の葛藤も感じないかのように。やがて、彼女の死体は車に載せられ、病院へと運ばれてゆく。
家の戸口で見送っている面長な母の顔、臆病そうに半分だけガラス戸から顔をのぞかせている父。その二人の姿が雨の中を次第に後ずさりしはじめた。
さよなら、私は、小さくつぶやいた。
「からっぽになっちゃったね」
あれはいつの解剖だっただろうか。深夜の解剖室で突然背後から声をかけられたことがあった。私はちょうど腎臓から脂肪を引き剥がしているところだったが、手をとめて振り返った。
「どうされました?」
解剖台の上には、私によって体を開かれた若い女性の遺体が横たわっていた。そばに彼女の主治医であった女医が佇み、がらんどうになった体腔を見下ろしていた。
「いや、ほんとうに臓器を全部とっちゃうんだな、って……ううん。べつに先生を責めているわけじゃなくて……なんというか……何なにもなくなっちゃって……彼女だったものが……なにもなくなっちゃって……」
彼女から取り出した臓器のかたまりは、私の右手にあった。私はこれからこの塊をそれぞれの臓器に腑分けするのだ。
「ああ、それなら代わりに綿をつめますし、止血剤もまきますよ」
解剖の助手を務めた年配の技師が口を挟んだ。
「うん……そうなんだけどね……」
私ははやく作業に戻りたかった。
「そうですね。やはり全ての臓器を検索する必要がありますので。ただ、標本にしない部分は時間が許す限り戻しますよ。遺族にはすこしお待ち頂くかもしれませんが」
そう言い背を向けた私に彼女はつぶやいた。
「うん……よろしくね」
女としての臓器や、重要な内臓を取りのぞかれた私の体は、どんな意味をもっているのだろうか。
吉村昭『星への旅』は、噎せ返らんばかりの死の腐臭が立ちこめた短篇集である。そこに収められた「少女架刑」は、死んだ少女の視点から、解剖により自らの体がその形を喪ってゆくまでを、あくまで即物的に、透徹した筆致で描いている。死体を取巻く「生」の喧噪と薄い膜で隔てられたかのような少女の静かな語りは、「死」の孤独を浮かび上がらせる。
解剖により彼女は徐々に臓器を抜き取られ、空虚な体腔は茶色の組織固定液で満たされてゆく。
「私の体の役目は、まだ終らないのか……」
そう独りごちながら、自分の体を弄る者に対し、時に羞恥を、時に劣等感を感じつつ彼女は常にその者たちを見ている。
――あのとき、私は彼女にあまりにおざなりな返答をしたのではないだろうか。

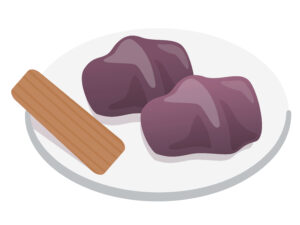




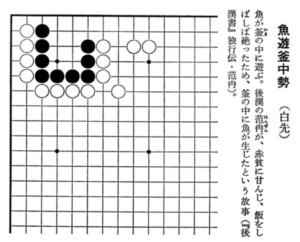
※コメントは最大500文字、5回まで送信できます