蘇東坡が呂微仲を尋ねたとき、微仲はちょうど昼寝中であった。長い間待たされてから、やっと微仲が出てきたので、東坡は菖蒲盆の中で飼われている緑毛亀を指さして、
「この亀はどこにでもいるものですね。眼が六つあるものはなかなか手に入りませんが」
と言ったところ、微仲が、
「六眼亀というのはどこにいるのかね?」
と問うたので、東坡は言った。
「昔、後唐の荘宗(李存勗)の同光年間の時、林邑國が六眼亀を献じたことがございますが、ちょうど敬新磨が御殿の下におりまして、即興でこう言ったとのことです。『みなさまお静かに。亀の子がなにか言っております。ほう、なになに。目が六つあると目を覚ますにも人の三倍かかる、と申しているようですな』」
東坡謁呂微仲,值晝寢,久之方出見,便坐。有昌蒲盆豢綠毛龜,坡指曰:「此易得耳,若六眼則難得。」微仲問:「六眼龜出何處?」坡曰:「昔唐莊宗同光中林邑國嘗進六眼龜。時敬新磨在殿下,獻口號云:『不要鬧,聽取這龜兒口號。六隻眼兒睡一覺,抵別人三覺。』」
『五雜俎』卷十六 事部四
昼寝のせいで長いこと待たされたのを、六眼亀にかこつけてからかったのである。
「六眼亀」は、『山海経』の注に「吳興郡陽羨縣の君山山頂にある池に、三本足で眼が六つある亀がいる」とあり*、また『舊唐書』に「大足元年、虔州の別駕が六眼亀を得たが、一晩たったらいなくなっていた」とある**。
* 『山海經廣注』「今吳興陽羨縣有君山山上有池水中有三足六眼龜鱉龜三足者名賁出爾雅」
** 『舊唐書』巻三十七「大足元年,虔州別駕得六眼龜,一夕而失。」
この「六眼亀」だが、ふつうに考えて六つ目の亀がいるわけがないので、目と見紛うような模様が四つあるのだろう。屈大均はこの六眼亀について「本当は目はふたつなのだが、黄金色で楕円形の模様が四つのあり、その中に黒い点があるので、本当の目と見分けがつかず目が六つあるように見える」と言っている***。ということはヨツメイシガメ Sacalia quadriocellata のことのようだ。
***『廣東新語』巻二十三「有六目龜,出欽州,本兩目,其四目乃金黃花紋,圓長中黑,與真目排比,狀似六目,故名。」

きれいな白目の中に黒があって、たしかにこれは六つ目と思ってもしかたない。
平凡社東洋文庫の岩城秀夫訳『五雑組8』は良い本なのだが、この部分の訳にはいくつかおかしな点がある。
まず、「呂微仲」が「呂徴仲」になっている。微仲は字で、名は大防である。呂大防(1027-1097年)は京兆府藍田県の人。仁宗皇祐元年の進士で、翰林学士などをつとめたが、のち左遷され循州(今の広東省)で客死した。
次に「中林国」という知らない国が出てくる。「同光中林邑國」の句読を誤るとは思えないから、先の「呂徴仲」と併せ、訳者の責ではなく底本がおかしいのだろう。
また、それに続く部分。
鬧を要せず、這の亀児の口号を聴き取らん、六隻の眼児、睡りて一たび覚むれば、別人の三たび覚めたるに抵らん、と
最初に読んだとき、『「六隻」の「眼児」とは何だ?』と首をひねったことを覚えている。ややあって『舞姫』に「曾て大学に繁く通ひし折、養ひ得たる一隻の眼孔もて」とあるのを思いだし、ここはおそらく「六隻の眼」を持つ「(亀の)児」という意味なのだろう、と思い返したが。言うまでもないが、「一隻眼」とは優れた見識のこと。鷗外にケチをつけるわけではないが、「一隻眼」はそれでひとつの語であり、「の」は無用、「孔」は蛇足である。
現代では「隻」の用法は船を数えるときの助数詞が主で、ほかは「隻眼」「片言隻句」くらいしか用いられないので、ひと続きにして直訳せず「六つの眼がある亀の子」程度でよかったのではないか。一応訳者を弁護すると、複数の眼を数えるのに「隻」を用いることは普通にあって、「三隻眼」(『封神演義』の聞仲など)や「四隻眼」(項羽や舜など)はよくある表現である。
あと、これは好みの話かもしれないが、訳文が固いと感じた。
そもそも「事部四」は戯謔を集めたものであり、前後の話はいずれもクスッとくる笑話である。東坡も、自分を待たせた事を責めているわけではなく、ちょっとからかっただけである。実際、この話を引いて「微仲は大笑いした(呂大笑)」と後ろに勝手にくっつけている本もある(『貴耳集』)。そして何より、ここで出てくるのが敬新磨だからである。
敬新磨は後唐の李存勗に仕えた宮廷藝人である。『新五代史』伶官傳に彼の逸話が残されているので、いくつか紹介してみよう。
莊宗好畋獵,獵于中牟,踐民田。中牟縣令當馬切諫,為民請,莊宗怒,叱縣令去,將殺之。伶人敬新磨知其不可,乃率諸伶走追縣令,擒至馬前責之曰:「汝為縣令,獨不知吾天子好獵邪?奈何縱民稼穡以供稅賦!何不饑汝縣民而空此地,以備吾天子之馳騁?汝罪當死!」因前請亟行刑,諸伶共唱和之,莊宗大笑,縣令乃得免去。
またこんな話もある。ちょっと言葉を補って訳す。
新磨嘗奏事殿中,殿中多惡犬,新磨去,一犬起逐之,新磨倚柱而呼曰:「陛下毋縱兒女囓人!」莊宗家世夷狄,夷狄之人諱狗,故新磨以此譏之。莊宗大怒,彎弓注矢將射之,新磨急呼曰:「陛下無殺臣!臣與陛下為一體,殺之不祥!」莊宗大驚,問其故,對曰:「陛下開國,改元同光,天下皆謂陛下同光帝。且同,銅也,若殺敬新磨,則同無光矣。」莊宗大笑,乃釋之。
『新五代史』伶官傳第二十五
要するに「おい、この犬はお前らの仲間だろ。なんとかしてくれよ」ということである。コイツも大概いらんことを言うヤツである。
莊宗大怒,彎弓注矢將射之,新磨急呼曰:「陛下無殺臣!臣與陛下為一體,殺之不祥!」莊宗大驚,問其故,對曰:「陛下開國,改元同光,天下皆謂陛下同光帝。且同,銅也,若殺敬新磨,則同無光矣。」莊宗大笑,乃釋之。
『新五代史』伶官傳第二十五
ところで、新磨を噛もうとしていた犬はどこに行ったのだろう。
機知と諧謔に富んだ彼の逸話を読んでいると、カンブン調に「鬧を要せず、這の亀児の口号を聴き取らん」よりも、もうちょっと柔らかく訳してもよいのではないか、と思う。笑い話まで荘重なテイで訳するのはかえって滑稽である。
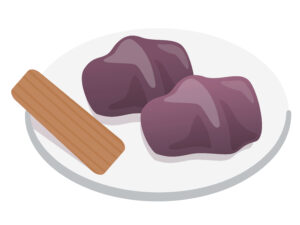




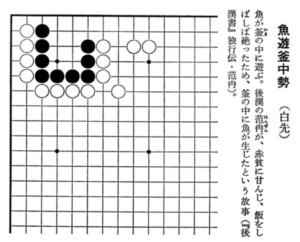
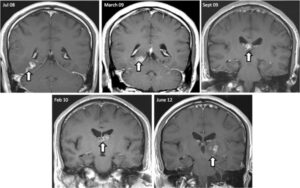

※コメントは最大500文字、5回まで送信できます