斉の景公は、都の南郊にある牛山に登った時、北のかたに都の街なみを見おろして、涙ながらにこう言った。
「なんと美しい国だろうか。樹木は青々と茂っているというのに、どうして移ろいゆくまま、この国を後にして死ななければならないのだろう。もしこの世にはじめから死という定めがなければ、わたしもここを離れどこにも行かなくて済むというのに」
従者の史孔や梁丘拠らはそれを聞き、もらい泣きしながら言った。
「わたくしどもは、殿のお恵みのおかげで生きておりますが、たとえ野菜屑や腐りかけの肉しかなく、駄馬やぼろ車にしか乗れないとしても、決して死にたいとは思いません。まして殿のこととなれば、なおさらのことでございましょう」
ところが晏嬰だけは、そばでそれを聞きながら笑っているので、景公は涙をぬぐいながら晏嬰をぐっと見すえこうなじった。
「わたしは今日この山に遊んで悲しい気持になった。そして史孔も梁丘拠もみなわたしと一緒に泣いてくれているのに、そなただけがひとり笑っているのは、いったいどういうわけだ」
すると晏嬰はこう答えた。
「もし、賢い王がいつまでも国を治めることができるならば、この国を開いた太公望や、覇者となった桓公が永久に斉の国を統治しつづけておられましょう。
もし、勇敢な王がいつまでも位にあることができるならば、荘公や霊公がきっとそれをなさっていたでしょう。
もし、賢者や勇者がいつまでも斉の王ならば、あなたなどは蓑笠をつけて田畑に立ち、ただ百姓仕事に心を費やすだけで、『死にたくない』なぞと考える暇はありますまい。まして、あなたが王位につかれることなど、ありえないことです。
かわるがわる位につき、かわるがわる位を離れるからこそ、あなたの番が回ってきたのです。それなのにあなただけが『死にたくない』といって涙を流すのは、自分勝手というものです。
わたくしは、自分勝手な殿さまと、それにこびへつらう臣下と、この二つのものを見ました。この恥ずべきものを前にすれば、笑うほかにしかたがないではありませんか」
晏嬰の言葉を聞いた景公はすっかり恥じ入り、罰杯をあげて己を責めるとともに、二人の家来を責めて、それぞれ二杯の罰杯を飲ませた。
――『列子』力命篇
『列子』を読んだのは、たしか二十前後のことだったはずである。当時は景公をやりこめた晏子の言葉を痛快に思ったものだが、四十の声を聞くようになると、晏嬰の言はどこか一面的なもののように思えてならない。
牛山の山頂での楽しい宴会の最中、なぜ景公は悲しみに襲われたのだろうか。
景公が挙げているのは、現世の豊かな生活を失うことに対する懼れである。従者二人の「私たちのように貧しい暮しをしていても、生に執着するというのに」という言葉もまた、それを裏付けている。とすれば、「人間にとって死は必然であり、前人が去ったからこそ、今あなたの楽しみがあるのです」と諭した晏嬰の言葉は、この文脈において正当な指摘である。
しかし、晏子は「あなたは賢者でも勇者でもなく、その位にあるべき人間ではないのに、偶然得た地位にしがみつこうとは嗤わせる」と口を極めて景公を嘲弄し、従者もそれに巻きこまれている。あまりに嗜虐的であり、景公が感情的に反発することなく折伏されたことがむしろ不自然に思われる。
この『列子』の挿話は、『晏子春秋』および『春秋左氏傳』に原型となった話がいくつか存在する(下掲)。それらを読んで私が感じたのは、描写が詳細になるとともに、この問題が景公個人の問題に矮小化され、悲しみの原因も、物質的な所有の喪失に限定されるようになってはいないか? ということである。ここで重要な働きをしているのが、二人の従者の登場である。彼らは主君の悲哀を「快楽の放棄」によるものと解釈し、それを讀者に提示する。そして晏嬰の返答によってその解釈が固定化され、この説話が完成しているのである。
歓楽極まったとき哀情生ずるのは、別に景公だけではない。漢の高祖は、天下を統一し沛に立ち寄った際、酒宴のなか自ら作詞した「大風歌」を歌いながら幾筋もの涙を流している
高祖還歸,過沛,留。置酒沛宮,悉召故人父老子弟縱酒,發沛中兒得百二十人,教之歌。酒酣,高祖擊筑,自為歌詩曰:「大風起兮雲飛揚,威加海內兮歸故鄉,安得猛士兮守四方!」令兒皆和習之。高祖乃起舞,慷慨傷懷,泣數行下。
『史記』高祖本紀
同じ君主と言っても、高祖の涙は景公のものとはだいぶん違うようである。
曹子建もまた華やかな酒宴の中、我が身のままならぬことを思ってか「箜篌引」を詠んでいる。
置酒髙殿上 酒を置く髙殿の上
親友從我遊 親友 我に從いて遊ぶ
中廚辦豐膳 中廚 豐膳を辦え
烹羊宰肥牛 羊を烹 肥牛を宰す
秦箏何慷慨 秦箏何ぞ慷慨なる
齊瑟和且柔 齊瑟和にして且つ柔なり
陽阿奏奇舞 陽阿 奇舞を奏し
京洛出名謳 京洛 名謳を出だす
樂飲過三爵 飲を樂みて三爵を過し
緩帶傾庶羞 帶を緩めて庶羞を傾く
主稱千金壽 主は稱す 千金の壽
賓奉萬年酬 賓は奉ず 萬年の酬
御殿に酒宴を張り、親友を招き共に楽しむ。
宮中の厨房はたくさんの料理を揃え、
羊を煮たり大きな牛をさばいたりと賑やかである。
秦の箏は何とはげしい音がすることだろう。
一方で齊の瑟はなごやかに柔らかな音を奏でている。
陽阿の踊り子は妙なる舞を奏し、洛陽の歌い手は見事な歌を歌う。
楽しみ飲んで大杯三献を空にして、
帯を緩めて数々の料理を平らげる。
主人は「千金の長壽あれかし」と杯を献じ、
賓客は「萬年の繁栄あらんことを」と返杯を奉る。
久要不可忘 久要は忘る可からず
薄終義所尤 薄終は義の尤むる所
謙謙君子德 謙謙たるは君子の德
磬折欲何求 磬折して何をか求めんと欲す
驚風飄白日 驚風 白日を飄えし
光景馳西流 光景 馳せて西に流る
盛時不可再 盛時 再びすべからず
百年忽我遒 百年 忽ち我に遒る
生在華屋處 生在しては華屋に處り
零落歸山丘 零落しては山丘に歸す
先民誰不死 先民 誰か死せざる
知命復何憂 命を知らば 復た何をか憂えん
古くからのつきあいを忘れてはならぬし、
昔からの友人と疎遠になれば不義理と誹られるだろう。
そうやってあちこちに気をつかうのは君子の美徳だろうが、
そんなにぺこぺこ頭を下げて何を求めようというのか。
疾風は白く輝く陽を吹き飛ばし、
日の光はあっという間に西に沈んでゆく。
人生の良い時は二度と戻らず、
年月はたちまち経って我が身に迫る。
生きているうちは豪華な家に住んでいても、
死ねば山丘の墓に帰るのだ。
昔の人で死ななかった者がいただろうか。
天命を知っておれば、これ以上何も憂えることなどない。
山の頂から広きを臨めば、千古変わらぬ光景を古人も眺めたことに思いを馳せるであろうし、青々と茂る木々を見渡せば、四季の移ろいと人同じからぬことを思うのが君子ではないだろうか。ただ景公だけが、現世の欲望を思って悲しむというのは、説話の目的上しかたないとは言え、私には不自然に思える。
――これは私の勝手な投影であり、公平に見れば晏嬰の言が正しいことは言うまでもない。ただ、もしかすると、景公も「それだけじゃないんだけどなぁ」という思いと共に罰杯を呷ったのかもしれない、と、ふと思ったのだった。
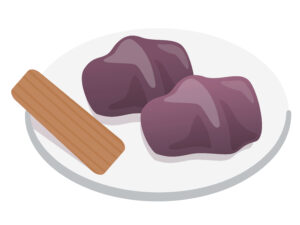




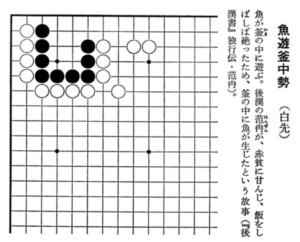
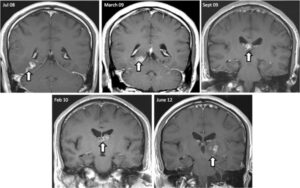

※コメントは最大500文字、5回まで送信できます