最近とんと聞かなくなったが、夏の昼どきになると、
わらびーもちー
わぁらぁあびぃいいもちぃいい
つめたくてぇー おいしいよっ!
と流しながら街をぐるぐる回る軽トラックがいたものである。
それを聞くたび、子供心に「わらび餅は美味しいけど毎日食べるというものでもないし、そんなに高いものでもない。あれで採算が取れるのだろうか」と余計な心配をしていたのだが、理科教師の父によれば「ああいうのは本当のわらびの粉なんか入ってなくて、イモのデンプンから作ってるんだ」ということであった。だから少しでも売れれば儲けが大きい、ということらしい。
なぜそんなことを思い出したのかというと、羅山の『丙辰紀行』(元和二年、1616年)を読んでいたとき、西坂(新坂、現在の静岡県掛川市日坂)の項に「この町ではわらび餅が名物だが、実はわらびの粉に葛粉を混ぜてつくっている」と書かれていたからである。
此所の民、わらび餅をうる。往還のもの飢をすくふ故に、いにしへより、新坂のわらび餅とて、其名あるものなり。或は葛の粉をまじへて蒸餅とし、豆の粉に鹽かてて旅人にすすむ。人その蕨餅なりと知りて、其葛餅といふ事を知らず。(中略)
『丙辰紀行』
婆叫焦兮婦喚烘
停人鄙食在途中
憑誰救得西山餓
馬首吹來餅餌風
婆は焦げたりと叫び、婦は烘れりと喚く
人を停むる鄙食途中に在り
誰に憑りてか救ひ得ん 西山の餓
馬首吹き來る 餅餌の風
茶屋の婆さんは「炙りたてだよ」と声を張り上げ、おかみさんは「こちらも焼けたよ」と大きな声で呼びかける。ここには旅人が思わず足を止めてしまう鄙びた名物がある。さてどの店に行けばこの西山の餓えを満たすことができるだろう、と馬を進めれば、風に乗って餅のいい匂いが我が鼻をくすぐる――くらいか。
「西山餓」は『史記』伯夷傳の故事より。周の武王が殷の暴君紂王を討とうとしたとき、伯夷・叔斉の兄弟はそれを諫めた。しかし聞き入れられなかったため、兄弟は周の粟を食うのを恥として西山に隠れ、わらびを食べていたがついに餓死したという。だから漢詩の中に「蕨」の字がなくても、この「鄙食」(田舎の食べもの)の「餠餌」(モチやダンゴ)はわらび餅だよ、とわかるようになっているのである。
一読して「なるほど。人のやることは今も昔も変わらんのだなぁ」と思わず苦笑してしまった。同時代の記録を見ても、山崎闇斎は『遠遊紀行』で「此ノ坂ノ蕨餅、古來ノ名物也。然ニ葛ヲ以之ヲ誑ク」(振りがなは引用者による)と書いており、松江重頼も『毛吹草』で「遠江國 西坂葛餅」とだけ記している。実は葛餅であったことはわりと知られていたようだ。川柳子にも
物の名もところによるか新坂の蕨のもちハよその葛餅
とからかわれている。
デンプンになってしまえばもはや蕨か葛か分からないだろう、と私などは思うのだが、むかしの人は「あっこれは葛餅じゃないか!」「むむっ、葛粉が入ってるな!」と気づいたものらしい。この時代の本を読んでいると、貧しい地方の代名詞として、あるいは飢饉の時の慣用句として「葛蕨の根を掘って食い」の字句を散見するから、当時の人は両者の味に慣れ親しんでいたのかもしれない。
しかしなぜ葛を混ぜるようになったのだろうか。
羅山より前の本を見てみると、たとえば里村紹巴の『富士見道記』(永禄十年、1567年)には「日坂に至りぬ。商山の古蕨を用ゐ」とあり、葛の混入云々の話は出てこない。商山とは上で出てきた西山と同じく中国の山で、秦末の戦乱を避けて東園公・綺里季・夏黄公・甪里先生という四人の老人が身を隠したところとして有名である。四人ともヒゲもマユも白かったので四皓(皓は「白い」の意)と呼ばれた。のち漢の高祖が太子盈を廃そうとしたとき、太子の生母呂后は張良と謀って四皓を招き、太子の補佐として仕えさせた。高祖は自分が招いても応じなかった四皓が太子に仕えていることを知り、太子の廃立を思いとどまったという。閑話休題。四皓が山でワラビを食って生活していたという話は知らないが、まあ食っていてもおかしくはない。
さて、日坂のわらび餅の最も古い記録とされる『東國紀行』ではどうだろうか。これは連歌師宗牧が晩年関東に下向したときの記録で、天文十四年(1545年)の成立である。
宗牧は日坂のわらび餅(蕨もちゐ)にいたく感心して歌を詠んでいる。
日坂とかいふ茶屋に休みて。跡なる荷物など待つほど。此山の名物なりとて。蕨もちゐと云ふものしすまして出したり。一年もさ有りけんなど。賞翫も一入。只にはいかがとて。
年たけてまたくふべしと思ひきや蕨もちゐも命なりけり
『東國紀行』
歌は「この年になってまたわらび餅を食べることができるとは。長生きはするものだなぁ」の意。言うのもヤボだが新古今和歌集の「年たけてまた越ゆべしと思ひきや命なりけり小夜の中山」にかけているのである。小夜の中山は日坂のすぐ東にある。宗牧には何か予感があったのかもしれない。彼は翌年旅先の下野国佐野で客死した。
秀吉による統一と関ヶ原の合戦を経て乱世はいったん小康を迎えた。それに伴い東海道の人の流れが活発になり、日坂の名物わらび餅の需要が増大したため、現地産のわらびだけでは需要を満たせず葛を混ぜようになったのかもしれない。

ここまで書いて今さら気づいたのだが、日坂と言えば金谷と掛川の間である。ということは私は以前そう遠くないところに住んでいたらしい。しかし思い返しても日坂のわらび餅について何も聞いたことがない。食い意地の張った私であるから、もし有名な菓子があるなら噂だけでも覚えていそうなものだ。もしかすると既に廃れてしまったのだろうか。
これまで戦国時代から江戸初期にかけての本を見てきたから、それより後の本を調べれば日坂のわらび餅のゆくえについて何かわかるかもしれない。
というわけで『名將言行錄』を見ると、日坂のわらび餅に関するおもしろい話が載っていた。
加賀藩の二代藩主、前田利常が江戸に向かう道すがらのことである。日坂宿に立ち寄ってわらび餅を食べたところ、まさに格別の美味であった。殿様大いに喜び「これを作ったのは誰か」と尋ねたところ、七十あまりの老女が連れられてきたので、彼女を一緒に連れて行くことにした。どうやって連れて行くのかというと、長持(蓋のついた長方形の大きな木製の箱)の上に毛氈を敷き、そこに老女を座らせ、前後ふたりに担がせるのである。赤いフェルトの上にちょこんと座った老女がえっさほいさと担がれて運ばれてゆくのであるから、沿道「あの婆さんは誰だ」と行く先々で大評判になった。「どうも日坂でわらび餅を作っている婆さんらしい」とは伝わったものの、なぜ担がれているのかはさっぱり分からない。
そうして道を進み江戸も近くなったころ、殿様は老女をねぎらった上で銀子二十枚を与え、駕籠で日坂に送り返した。道々「あの婆さんが戻ってきたぞ」と人が群がり、事情を尋ねられた老女は「わらび餅の褒美にたくさん銀子を頂いてありがたいことじゃ」と語った。このことから日坂のわらび餅の名が広く知られるようになり、また前田の殿様の御意にかなえば大いに褒美が頂ける、と街道の人々の励みにもなったという。人の好奇心を上手くつかった宣伝法である。
さて、前田利常や林羅山の時代から二百年以上たった安政二年(1855年)、清河八郎もまた日坂宿を訪れてわらび餅を食べたと日記に記している(『西遊草』)。
その日は夜明けから一里二十九町歩いて日坂宿に着いたらしい。一里二十九町は今の7kmほどで、日坂のあたりは山道であるから、まあまあ大休止といったところだろう。そしてその日は今の暦になおせば9月2日である。残暑のなか、山道を登ってすこし疲れたところに、きな粉のかかった塩っ気のあるわらび餅が出てくるのである。これだけ条件が揃えばさぞかし美味く感じるだろう、と思いきや、清河はいつもの辛辣な口調で「大そうまずい。銭失いの喉けがしであった」と酷評している。
清河は滅多に物を褒めないので割引いて考える必要があるが、日坂のわらび餅を酷評しているのは残念ながら彼一人ではないのである。
清河より百年ほど前に土御門泰邦という陰陽家がいた。安倍晴明の後裔という。宝暦十年(1760年)、彼は勅使の随行員として江戸に下ったのだが、そのときの記録『東行話説』の中で彼もまた日坂のわらび餅を口を極めて罵倒しているのである。
彼はまず宿にケチをつける。「それにしても汚い宿だな。それに狭い。まるで行燈みたいだ」そして日坂宿の名物がわらび餅と知ると、「こんな風体の宿ではろくなものが出てこないだろうが、京に帰った時に『日坂のわらび餅はどうだった』と聞かれるだろうから食ってやる」とわらび餅を取り寄せたらしい。あとは原文を見てみよう。
扨こそ案の如く、言語道斷、頗る先日の柏餅に彷彿たり、いやしくも又懲もせずと人のおもはん程、恥かしく、紙に包みそと捨てよと、例の惟光を招きわたすとて、
名にめでゝねぶるはかりぞ蕨餅我こりにきと人に食はすな
(引用者がふりがなを補った)
食べ残しを紙に包んで従者(「惟光」とは従者一般を指す)に命じて捨てさせ、熱い湯を飲み胸をさすって急ぎ坂を下ったらしい。柏餅というのは、二川宿(三河國吉田、猿ケ馬場)で彼が食べた柏餅のことで、美味いとすすめられて食ってみたが「南無三さにもあらず、唯さく/\として、糠をかむが如し。少し臭みありて胸わろく、ゑづきの氣味しきりなれば、奇應丸を取り出し、かみて湯を吞み、漸うにたすかりぬ」と書いている。ついでに「馬糞を喰ったらこんなもんだろうなぁ」なんていう喝を残している。
いくら口に合わなかったからとはいえ食い物を捨てるのはどうかと思うが、それを措くと、清河とは違い土御門は美味いものは美味いと言うので、これは極端な反応であっても彼は実際に不味いと思ったのであろう。
加えて大正時代にも漫画家の細木原青起がこんな感想を述べている。
お椀の底に五六個の鶉豆大の餅が沈んで砂糖が振りかけてある。味に蕨と思はれる匂ひもなく、變哲もない代物であつた。
東京漫画会編. 東海道漫画紀行. 1922年. 朝香屋書店. p91
どうもこう見てくると、うるさ型で味にこだわりのある連中からすると日坂のわらび餅は「名物に旨い物なし」であったとのかもしれない。宗牧や前田利常が讃えたわらび餅がなぜここまで落ちぶれたのだろうか。
ひとたび人気になったはいいものの、需要の増大に対応するために混ぜものをしてしまい、そのため味が落ちて人々に嫌われた――というのは現代でもありそうな話である。
葛餅とわらび餅、私はどちらも好きで甲乙つけがたいが、江戸時代の人にとってははっきりした上下があったため「わらび餅に葛粉を混ぜるなんて!」と嫌われた可能性はどうだろうか。しかし『本朝食鑑』の蕨の項なんかを見ると「わらび餅の味は葛餅と遜色ない(味不減葛餅)」と書かれている。「不減」ということはむしろ葛餅の方がわらび餅よりやや上等という意識があったのではないか。ならばわらびの代用に葛が使ってあるならいいではないか、ということになりはしないか?
両者を混ぜることで食味に何らかの変化が生じた可能性はどうか。この仮説について真面目に検討するならば葛のデンプンとわらびのデンプンの特性について調査し、両者混交の割合による食感の変化について実験する必要がある――と思っていたのだが、ふと調べてみると南越前町立南越前中学校一年の谷﨑怜生氏による「わらび餅に適した澱粉とは?」という論文があることがわかった。すこしの事にも先達はあらまほしきことである。
谷﨑氏よれば、葛のデンプンはアミロース含量が多く、そのため調理後の時間経過によるデンプンの老化が早く進み、餅の透明感の減衰および生地の硬化が起こりやすいらしい。これが日坂のわらび餅衰退の原因かもしれない。
一方でイモやタピオカのデンプンなんかはアミロースが少なくアミロペクチンが多いため時間が経っても透明で柔らかい状態を保ちやすいとのことである。とすれば「わらびーもちー」も父が言うように「安いから」だけではなく、「作り置きが劣化しづらいように」という工夫の結果なのだろうね。



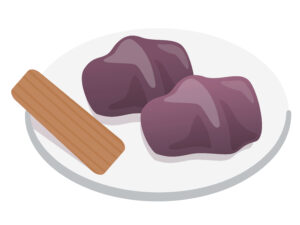



※コメントは最大500文字、5回まで送信できます