蘇軾、蘇轍兄弟は嘉祐六年(1061年)に制科に応じた。結果は、蘇軾は第三等、蘇轍は第四等合格であった。
「制科」とは科挙で拾い上げることのできない人材を登用するための試験制度で、宋代にしばしば行われた。科挙とは異なり他薦であり、蘇軾も欧陽脩らの推薦を受けている。試験は天子臨席のもと行われ、天子自ら出題した制策に対して答案をつくり、優秀なものが合格とされた。
合格者の成績は五段階に分けられた。蘇軾は三等であるから「まあそこそこやね」と思ったらマチガイである。「三等重役」とは違い、一等、二等は実際には名だけで、三等が最優等なのである。宋代において、制科第三等は蘇軾と呉育のほか数人しか出ておらず、進士の第一甲と同等の官が与えられた。なお、五等については、五等にするくらいなら落第させることが多かったので、たいていは蘇轍のように四等である。ちなみに杜牧(大和二年)も四等。
制科の説明はこれくらいにして、蘇轍が試験の際に提出した答案のうちのひとつ、「諸葛亮論」を見てみよう。蘇軾は蜀の出身であるから、定めし諸葛亮を讃えているかと思いきや、その評価の辛いのに驚いた。字句を補って訳すと以下のようになる。
信義をもって天下を取り、信義により天下を治めたのが周である。詐力(謀略と武力)により天下を掠め、それを守ろうとしたのが秦である。秦のように詐力より天下を得、周のように信義をもって天下を治めたのが漢である。信義と詐力を綯い交ぜにして天下を取ろうとしたこと、それこそが孔明の失敗であった。
曹操は、漢の威が衰えたのに乗じてその野望を剥き出しにした。孔明は、この時勢を恥じ、大義はどこにあるかを天下に示そうとした。当時、曹操の威は四海に満ち、東のかた許昌・兗州に拠り、南は荊州・豫州までその勢力は及んでいた。孔明が恃みにできたのは、わずかにその忠信によって、天下万民の心を掴むことだけだった。天下には義に殉じることを厭わない廉潔の士が居り、もとより彼らは曹氏に心服していたわけではなく、ただ権力によって押さえつけられていただけだであった。もし彼らが、孔明が立ち上がったことを聞けば、どれだけ遠くにいたとしても、その檄に応じて立ち上がっただろうし、そうすれば、たとえ小国であっても天下を相手にし得ただろう。天下を得るために無辜の人間を殺したりしないからこそ、忠臣義士はその人のために喜んで命を投げ出すのである。しかし、孔明は、劉表の喪中に、遺児の劉琮を襲って殺すことを劉備に進言した。劉備は劉表に遇された恩を思い、孔明の提案を退けた。次いで、劉璋に好意を以て迎え入れられるや、その信頼につけこんだあげく、益州を奪った。これでは、曹操のやっていることと何ら変りがないではないか。最初から、曹操と劉備では相手にならないことは、天下の誰もが知っていた。兵士の数は少なく、領土も狭く、戦の上手さも曹操に及ばない。ただ忠信だけが孔明の恃みであったが、それさえも、益州を騙し取ったために、義士たちの心は離れてしまった。これらの背信行為の後になって、東征軍を起こし、信義のありかを掲げて天下万民が呼応することを望んでも、それは無理というものである。
思えば、曹操が死に、曹丕が跡を襲ったときに、智謀を以て後継者争いにつけこむべきであったのだ。 かつて袁紹が死んだとき、曹操が、袁譚・袁尚兄弟の相克の争いにつけこんで両者を破ったように。曹操は臨終の際、曹丕と曹植に対し、袁兄弟の轍を踏まぬよう戒めなかった。その結果、曹丕と曹植はあのように激しい争いを起こし、親子兄弟は互いにいがみ合った。そんな彼らに天下の義士の心を掴むことなどできようもない。ほんの数十万金でよいのだ。金ををばらまいて一族重臣を巻きこんだ争いを起こし、おもむろに軍を起こして討つ。漢の高祖が項羽を破ったのと同じやり方である。孔明は信義を貫くことができなかったし、天下の心を掴むこともできず、また智謀によって魏の手足を切り落とすこともできなかった。何度も戦い、何度も志を遂げることなく敗れたのは、当然のことであった。
殷の湯王のように徳のある人間が、敵の弱みにつけこまないのは、大義に悖るからである。しかし、徳のない人間が同じ事をするのは、単に機を逸しているだけである。これは仁人君子を自認する者の陥りやすい陥穽である。かつて唐の呂温は、桓帝・靈帝時代の腐敗と失政が民を苦しめたことを考え、孔明は漢への忠誠を民に強制しなかったのだ、と言った。「もし魏がお前たちを慈しむのならば、我は魏に仕えよう。もしお前たちに害をなすのならば、我は魏を討とう」という心であったと。まさか、魏と蜀のどちらが大きかったか知らないわけではあるまい。このような絵空事をうそぶいていて、どうして天下を安んじることができようか。ああ! このような意見は所詮書生論である。取るに足らぬものだ。
取之以仁義,守之以仁義者,周也。取之以詐力,守之以詐力者,秦也。以秦之所以取取之,以周之所以守守之者,漢也。仁義詐力雜用以取天下者,此孔明之所以失也。
曹操因衰乘危,得逞其奸,孔明恥之,欲信大義於天下。當此時,曹公威震四海,東據許、兗,南牧荊、豫,孔明之恃以勝之者,獨以其區區之忠信,有以激天下之心耳。夫天下廉隅節概慷慨死義之士,固非心服曹氏也,特以威劫而強臣之,聞孔明之風,宜其千里之外有響應者,如此則雖無措足之地而天下固為之用矣。且夫殺一不辜而得天下,有所不為,而後天下忠臣義士樂為之死。劉表之喪,先主在荊州,孔明欲襲殺其孤,先主不忍也。其後劉璋以好逆之至蜀,不數月,扼其吭,拊其背,而奪之國。此其與曹操異者幾希矣。曹、劉之不敵,天下之所共知也。言兵不若曹操之多,言地不若曹操之廣,言戰不若曹操之能,而有以一勝之者,區區之忠信也。孔明遷劉璋,既已失天下義士之望,乃始治兵振旅,為仁義之師,東向長驅,而欲天下響應,蓋亦難矣。
曹操既死,子丕代立,當此之時,可以計破也。何者?操之臨終,召丕而屬之植,未嘗不以譚、尚為戒也。而丕與植,終於相殘如此。此其父子兄弟且為寇仇,而況能以得天下英雄之心哉!此有可間之勢,不過捐數十萬金,使其大臣骨肉內自相殘,然後舉兵而伐之,此高祖所以滅項籍也。孔明既不能全其信義,以服天下之心,又不能奮其智謀,以絕曹氏之手足,宜其屢戰而屢卻哉!
故夫敵有可間之勢而不間者,湯、武行之為大義,非湯、武而行之為失機。此仁人君子之大患也。呂溫以為孔明承桓、靈之後,不可強民以思漢,欲其播告天下之民,且曰「曹氏利汝吾事之,害汝吾誅之。」不知蜀之與魏,果有以大過之乎!茍無以大過之,而又決不能事魏,則天下安肯以空言竦動哉?嗚呼!此書生之論,可言而不可用也。
まず孔明の背信行為を咎め、ついでその智謀にも疑問を呈している。劉備の入蜀を主導したのは法正とされるが、もとは諸葛亮の提案であるのは確かである。曹操から曹丕への代替わりにあたって、孔明は全く無策ではなかったのだろうが、特に傳えられる所はない。蘇軾の言うことは決して間違ってはいない。
むろん、蜀の出だから諸葛亮を讃えなければならない、などという義理はない。彼の生きた北宋は曹魏正統論の華やかな時代であった。当時の輿論では、孔明や劉備は中国を統一できなかった敗者である。その敗者の失敗の原因を細かく分析し、批判する動機はなんだろうか。もちろん前車覆轍ということもあろう。相手を憎んでのことかもしれない。また、彼の失敗を惜しんで、ということもありえる。その真意はどこにあるのだろうか?
先に「八陣磧」について書いたが、蘇軾にも八陣磧について詠んだ詩がある。まずはそれを見てみよう。
平沙何茫茫,髣髴見石蕝。 平沙何ぞ茫茫、髣髴として石蕝を見る
縱橫滿江上,歲歲沙水嚙。 縱橫江上に滿ち、歲歲沙水嚙む
孔明死已久,誰復辨行列。 孔明死して已に久しく、誰か復行列を辨ぜん
神兵非學到,自古不留訣。 神兵は學んで到るにあらず、古より訣を留めず
至人已心悟,後世徒妄說。 至人は已に心に悟る、後世徒に妄說す
自從漢道衰,蜂起盡姦傑。 漢道の衰へしより、蜂起盡く姦傑なり
英雄不相下,禍難久連結。 英雄相下らず、禍難久しく連結す
驅民市無煙,戰野江流血。 民を驅りて市に煙なく、野に戰って江に血を流す
萬人賭一擲,殺盡如沃雪。 萬人一擲を賭し、殺し盡す雪に沃ぐが如し
不為久遠計,草草常無法。 久遠の計を為さず、草草常に法なし
孔明最後起,意欲掃羣孽。 孔明最後に起り、意羣孽を掃はんと欲す
崎嶇事節制,隱忍久不決。 崎嶇節制を事とし、隱忍久しく決せず
志大遂成迂,歲月去如瞥。 志大に遂に迂を成す、歲月は去って瞥の如し
六師紛未整,一旦英氣折。 六師紛として未だ整はず、一旦英氣折れて
惟餘八陣圖,千古壯夔峽。 惟八陣の圖を餘し、千古夔峽を壯とす。
平沙には広く草が生い茂り、岩や茅の束だけが点々と見えるだけである。これらの岩も、水が河に満ちる季節になると、河の流れに洗われ、やがてその姿を隠してしまう。孔明が死んでから長い時が過ぎ、岩がどのように並んでいたのか、もう誰にも分からない。たとえ当時のままであったとしても、神の如き用兵は、岩に学んでできるようになるものではない。真の秘訣というものは、その人の中にあるものであって、その人の死とともに滅ぶのである。後世の人間は、その遺蹟を見てああだこうだと議論するが、いずれも下らぬものである。
後漢が衰えてからというもの、数多くの姦傑が並び立った。彼らは互いに争い、禍が禍を呼んだ。その度に民衆は戦に駆出され、野にその屍を晒し、河をその血で染めた。やがて民衆は四散し、市に炊ぐ煙も絶えた。誰も彼もが刹那に身を委ね、人々は殺しあい、雪に水を注ぐように命が失われた。この中国を統一し、国家百年の計を為すことを考える者もなかった。
そこに孔明があらわれ、悪者どもを一掃しようとした。蜀漢は地方政権に過ぎなかったため、節制しつつその時が来るのを待たざるをえなかった。しかし、その志は国力を過ぎたものであったため、好機をうかがっているうちに、瞬く間に時は流れ、軍が整わぬうちに孔明は死んでしまった。今は、この八陣磧だけが遺され、夔州の峽を永遠に守っている。
ここでは、孔明の軍略とその志を讃え、彼が光復を成し得なかったことを八陣磧に託して惜しんでいる。先の「諸葛亮論」とは随分な変わりようである。どちらが真意なのか――いや、どちらも蘇軾の想いなのだろう。彼はまた「隆中」でこううたっている。
諸葛來西國,千年愛未衰。 諸葛西國に來る、千年愛未だ衰へず
今朝遊故里,蜀客不勝悲。 今朝故里に遊ぶ、蜀客悲に勝へず
誰言襄陽野,生此萬乘師。 誰か言ふ襄陽の野に、此の萬乘の師を生ずと
山中有遺貌,矯矯龍之姿。 山中に遺貌あり、矯矯たる龍の姿
龍蟠山水秀,龍去淵潭移。 龍蟠れば山水秀で、龍去れば淵潭移る
空餘蜿蜒蹟,使我寒涕垂。 空しく餘す蜿蜒の蹟、我をして寒涕を垂れしむ
孔明が蜀に来てから千年経った今でも、彼への敬仰はいまだ衰えることがない。今、孔明ゆかりの隆中に来てみれば、蜀からの旅人として悲しみの思いが抑えがたい。ああ、この襄陽の地に、天子の師たるべき孔明が生れると、誰が予想し得ただろうか。山に入れば、大志を抱きつつ雌伏していた孔明がここに居たのだと偲ばれる。伏龍ありし頃は山水もまた生気を宿していたが、龍が去るとその棲処もまた蜀に移ってしまった。孔明がかつて生きた足跡を辿りながら、私の目からは涙がとめどなくこぼれ落ちる。
孔明に対する純粋な仰慕を素直に表現している。また『東坡志林』を辿ると、蘇軾はいくつかの文章のなかで、孔明を聖人(孔子)になぞらえており、また劉備との君臣のあり方を讃えている。これらをどう解釈すればよいのだろうか。私は――勝手な思いかもしれないが――蘇軾が「諸葛亮論」で孔明の瑕疵を執拗に挙げているのは、郷里の偉人が大事を成し得ることができなかったことに対する痛惜の念から、という気がしてならない。まあ要するにツンデレだな。



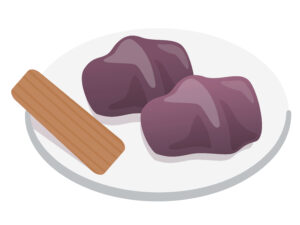



※コメントは最大500文字、5回まで送信できます