アメリカにいたころ、アジアンマーケットの食器コーナーでちょっと珍しいものを見つけたことがあった。なにかというと、フタのついた大きめの湯吞みである。
あっ、と手を伸ばしカゴに入れたのだが、そのココロは「これで茶碗蒸しをつくろう!」というものであった。そのマーケットは Chinese 御用達だったが、以前あちらの本で「雪盫菜」という食べ物を見かけたことがあったから、もしかすると中国でも茶碗蒸し用に使われているのかもしれない。
私は茶碗蒸しが好きである。食卓にあると楽しい、と言うべきか。
茶碗蒸しが楽しいのは「何を入れても構わない」ところである。作ってもらったものであれば、今度は「何が入っているかわからない」というのも嬉しい。
茶碗蒸しの具材としてパッと思いつくのは、ミツバ、しいたけ、タケノコ、エビ、鶏肉、百合根、カマボコ、ギンナン、サヤエンドウ、ホウレンソウ、ちくわ、カニカマ、ホタテ、薄く切ったニンジンやレンコン、焼き豆腐などさまざまである。もちろんこれらに限らない。小さな餅やウドンの切れっ端をいれてもいいし、水餃子なんかを1個2個放りこんでも良いかもしれない。

実家の茶碗蒸しはいつも大根の薄切りが底に敷かれていた。大根まで到達するとそこで終わりというサインである。ただ市販品や料理屋でそんな構造になっている茶碗蒸しに出くわしたことがないから、これはどうも母の独創のようである。
以前、酒席で茶碗蒸しの話になったことがあり、その大根の話をして
「五右衛門風呂のげすいた(下水板)みたいな感じですね」
と言ったら、それを聞いた歳の離れた友人は「五右衛門風呂って、あなたそんな歳じゃないでしょう」ハハハと笑っていた。ただそのとき私はちょっと不思議な感覚がした。五右衛門風呂は私は書物で知るばかりで、それこそ弥次さん喜多さんの時代のものだと思っていたのである。ところがそうではなく、どうも昭和四十年くらいまでは普通にあったものらしい。
ちなみにダイコンの件について後日母に訊いてみると、「モチが容器の底にくっつくのが嫌だから」ということであった。なるほど、それはたしかに reasonable である。(後日追記)おそらく母方の祖母が生まれ育った福岡県朝倉郡の蒸し雑煮は大根を下に敷くので、それから来ているのであろうと思われる。
アジアンマーケットの場面に戻ると、次に茶碗蒸しに何を入れるか考えなければならない。
もしここが日本のスーパーマーケットなら、具はよりどりみどりである。ただここはアメリカのアジアンマーケットである。ふむ困ったな、やはりミツバは欲しいが、などと野菜売り場を眺めていたところ、安いキノコが大量に売られているのに気がついた。
ただ何のキノコなのかさっぱりわからない。札が手書きの簡体字でくしゃくしゃっと書かれていて何も読めないのである。キノコの方は白色で根元から柄が別れ、銀杏型に折り重なっていた。マイタケを白くしたような形態である。よしれんキノコを摂取するのはこれを避くのが常識だが、まあまあスーパーの店頭で売られているものだから大丈夫だろう、Chinese も Japanese も身体のつくりはたいしてかわらんだろうし、とタカをくくって買って帰った。
家に戻ってさっそくキノコを刻み、卵液とダシと鶏肉を買ってきた湯吞みに入れ、鍋と皿を組み合わせた即席蒸し器に配置して火にかけた。
すこしたって蓋を取ってみたが、意外にも湯吞みの中身は元の姿を保っている。
「火力不足かな」と火を強めてさらに30分ほど待ってみた。しかし固まっていない。
これはどうしたことだろうか。かと言って捨てるようなもったいないことはできない。
思うに、入っているのは卵液とダシと鶏肉とキノコであるから、「まあ親子丼にでもするか」と中身をフライパンにあけ、強火でなんとなく固まったところを飯にかけ掻きこんだのだが、これはどうにも不味いシロモノだった。茶碗蒸しにするつもりであったから鶏肉やキノコに下味がついていないのと、一応それとなく固形になったとは言え、どうもグズグズしたできばえで、ずいぶん後悔しながら醤油をふりかけなんとか食べきったのだった。
しばらくして、ボスとの雑談の折に「こちらの卵は固まりにくいんでしょうかね。茶碗蒸しを作ろうとしたんですが、なかなか固まらなくて往生しました」と言ったが、「いや、そんなことはないはずだけどなぁ」と在米の長いボスは首をかしげていた。
帰国してからふとこのことを思いだし、「なぜ卵が固まらなかったのだろう」と調べてみたところ、こんな論文があった。
私は知らなかったが、マイタケに含まれるプロテアーゼは卵白の主成分であるオボアルブミンに対し強い分解作用を示し、またこのマイタケプロテアーゼは熱耐性が強いことから、茶碗蒸しに入れてしまうと固まらない、とのことであった。ということは、あのよしれんキノコはマイタケの仲間だったのかもしれない。確認するためには対照実験をせねばならぬが、さすがに、今さらそのキノコを求めて渡米する気にはなれない。
実家に帰ったとき、このことを得意げに話したのだが、母はまあそりゃそうだ、なんだそんなことも知らなかったのか、という顔をしていた。どうも主婦には常識であったようである。ただ不肖のせがれはウカツにも四十を超えて初めて知ったのであった。



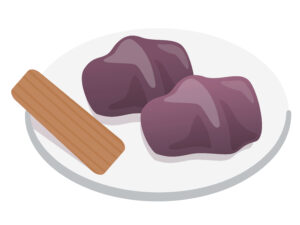



※コメントは最大500文字、5回まで送信できます