あるところに仇を避けて深山に身を隠している男がいた。白い月が昇り、清らかな風が吹くある夜のこと。男がふと見やると、白楊の下に幽霊がいた。男が地に伏せて身を隠すと、幽霊は彼の方に振り向いて言った。
「そんなところに隠れていないで出てきたらどうだ」
彼は震えながら答えた。
「あなたが恐ろしいのです」
「いちばん恐ろしいのは人間だよ。幽霊の何が恐ろしいものか。では訊くが、君をこんな山奥に隠れるような境遇に追いこんだのは人間ではないかね?それとも幽霊の仕業かね?」
幽霊はそう言い、ふっと笑うと姿を消した――。
朱青雷言,有避仇竄匿深山者,時月白風清,見一鬼徙倚白楊下,伏不敢起。鬼忽見之曰:「君何不出?」栗而答曰:「吾畏君。」鬼曰:「至可畏者莫若人,鬼何畏焉?使君顛沛至此者,人耶鬼耶?」一矣而隱。
『閱微草堂筆記』巻二
「夜中に死体の解剖とか怖くないですか」なんてことをたまに訊かれることがある。
「そうそう、こないだもめっちゃ怖いことあってな……」などと、大阪人としては適当に作り話のひとつやふたつでもして期待に応えたい気持ちがないでもない。が、実際にはそのような体験は一度たりとしてないというのが偽らざる所である。
午前三時、蛍光灯の明滅する解剖室で一人、遠くから遺体をのせたストレッチャーの近づいてくる音を聞いたり、体を開かれ臓器を抜かれた遺体を背に、取り出された臓器の塊を切り分けるといった作業は、もしかすると病理医以外の人によっては恐怖や好奇の対象なのかもしれない。
しかしこの仕事は、亡くなった人がなぜ死なねばならなかったのか、その原因を究明し他者の治療の糧とするために行っているのである。霊感とかそういうオカルト的な雑念が入る余地などどこにもありはしない。私が若いころであればおそらく「何か勘違いしとりゃせんかね」と青筋立てて怒ったに違いないが、今は「まあしょうがないのかな」くらいにしか思わない。一般人からすると「解剖」「死体」と聞くとそういう興味を抑え難いであろうから。
だから「死体の解剖とか怖いでしょう」というnaiiveな質問には「いやぁ霊感とかさっぱりなもので」などとはぐらかすのを常としている。



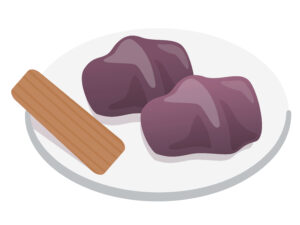



※コメントは最大500文字、5回まで送信できます