ナポレオン戦争を舞台としたイギリスの小説を読んでいると、”the Frogs” という単語がちょこちょこ出てくる。これは “Monsieur Jean Crapaud” と同じくフランス人の蔑称で、「カエル野郎」「カエルを喰う連中」ということである。
‘Silence!’ ordered Bush at that very moment. There was a certain strangeness about his voice as he continued, because he did not want his words to be overheard in the Frenchman, and so he was endeavouring to bellow sotto voce. ‘Show the Frogs how a British crew behaves. Heads up, there, and keep still.’
C. S. Forester. Hornblower and the Hotspur. 1962.
フランス料理にカエルが出てくる印象はないのだが、後脚を使った料理があるらしい。17, 18世紀にはエスカルゴもフランス料理として定着していたはずだが、なぜ「エスカルゴ喰い」とか「マイマイ野郎」ではなく「カエル野郎」なのだろう、とすこし不思議に思った。もしかするとイギリスでもカタツムリを普通に食べていたのだろうか。まあ “Frogs” の方が言い易いから、なんて単純な理由が一番ありそうである。
わが国でも昔はカエルを食べることもあったようだ。『公事根源』元日節會に「應神天皇十九年十月に、吉野の宮に行幸ありし時、國栖人參りて一夜酒を奉りて、歌をうたひける。此の國栖人山の木の實を取りて食ひ、又かへるを煮て、名をば毛瀰となづけて上味ありとて食ひけるとかや」と書かれている。煮たあとどう調理するのかはわからない。
現代ではジビエ料理店で時折唐揚げを見かける程度だろうか。私も物は試しと同輩とともに一度食べてみたことがある。中国で「田鷄」と呼ぶとおり、味は鶏のササミに似ているのだが、独特の癖がありあまり感心しなかった。またそれなりの値段がしたにもかかわらず、出てきたのはほんの少しで、「なんや少ないなぁ」「まあ一匹からそうたくさんは取れなさそうだし」「脚が8本あるカエルをつくるしかないな」などと同輩と話したおぼえがある。そういえば李賀「苦晝短」に「食熊則肥,食蛙則痩。」の句があるが、これも量が少ないことを言ったものだろうか。

カエルを食べる(食べない)話にこんなものがある。
盧伯平(文璧)至正初,尹荊山日,忽有一巨蛙登廳前,兩目瞠視,類有所訴者。令卒尾之行,去縣六一裏,有廢井。遂跳入不出,既得報,往集裏社汲井,獲死屍,乃兩日前二人同出為商,一人謀其財而殺之。掩捕究問,抵罪。死者之家屬雲,其在生不食蛙,見即買放。豈一念之善,為造物者固已鑒之。蛙能雪冤,良有以也。
『南村輟耕録』巻十五
残念ながら私はカエルの唐揚げを食べてしまったので、カエルの報恩を受けることはできなさそうである。まあ、しかし、カエルを食らわばなんとやらで、古い本には肉芝(一万年生きたヒキガエル)を食べれば四万年の生が得られると書かれているから、そちらを目指すとするさ。
『抱朴子』巻十一「肉芝者,謂萬歲蟾蜍,頭上有角,頷下有丹書八字再重,以五月五日日中時取之,陰乾百日,以其左足畫地,即為流水,帶其左手於身,辟五兵,若敵人射己者,弓弩矢皆反還自向也。(略)此二物得而陰乾末服之,令人壽四萬歲。」
……して、一万年生きたヒキガエルというのはどこにいるのかね?



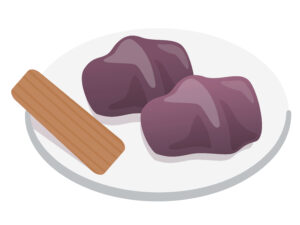



※コメントは最大500文字、5回まで送信できます