むかし向田邦子が「子供のころ熱燗の加減を見るのが上手だったので『この子はすぐにでも嫁に行けるねぇ』と言われた」云々と書いていたのを読み、台所でサトイモの皮を剥いていた母に「お燗の付け方って習った?」と尋ねたことがあった。まだ酒も飲めないガキのくせに妙なことを訊いたものである。
返答は覚えていないが、両親が熱燗をやっている姿はついぞ見かけたことがないから、おそらく無縁だったのであろうと思われる。私も当然習わなかったので、熱燗を一杯という時は見よう見まねで電子レンジのお世話になっている。
熱燗で思い出したが、江戸時代中期の俳人、炭太祇の句にこんなものがある。
身の秋やあつ燗好む胸赤し
『太祇句選』
初読時「なんかチグハグな句だな」と思った覚えがある。いま見返してもその思いは変わらない。
秋が身に沁みいるころ、熱燗をやっていい気分になり、はだけた着物の隙間から赤く火照った胸が覗く――という句だと思うのだが、なぜ「身の秋や」なのだろう。
「身の秋」は「身の飽き」に通じることから、人に見棄てられた身を秋の寂しさにたとえたものと解釈するのが普通である。たとえば『蜻蛉日記』に「身の秋をおもひみだるる花の上の露のこころはいへばさらなり」とある。他の女の家に通う藤原兼家に対して、道綱母が「あなたに飽きられた身のつらさに思い乱れている様子が表にあらわれているのですもの、その露のようにはかない心の中は言うまでもないでしょう」と言っているのである。
和歌だけではなく、俳句でも「身の秋や今宵をしのぶ翌もあり」(蕪村)のように使われる。道綱母のように直接的に人に見棄てられたのではなくても、身の不遇や衰えを指すのである。
というわけで、この「身の秋や」と、二句、結句の熱燗をやって胸をはだける豪放な情景が私にはよく繋がらないのである。強引に「身の秋や」に合わせるなら、憂いをまぎらわそうと熱燗を呷り、台につっぷしたその着物の隙間から赤くなった胸が垣間見える、と解釈できなくもないが、どうも捻りすぎな気がする。
うーん。結局のところ、太祇の「身の秋」は説明しすぎると却って本意から遠ざかるのだろう。
気まぐれに胸の赤くなるような、そんな季節のゆらぎとして受けとめておくのがよさそうだ。
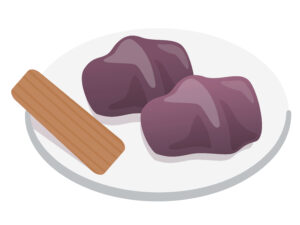




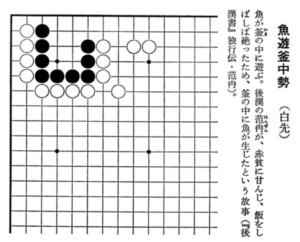
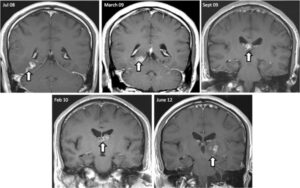

※コメントは最大500文字、5回まで送信できます