張献忠は子供のころ、父親の棗売りについて蜀に来たことがあった。父親が驢馬を郷紳の門前につないでおいたところ、驢馬が糞尿で石柱を汚した。その家の下僕は怒り、張献忠の父親を鞭打つと、手で糞をすくって捨てるよう命じた。張献忠は柱の陰で下僕を睨みつけていたが、帰るとき「次に来たら貴様らをひとり残らず殺して、この恨みを晴らしてやる」と誓った。
張献忠は成人すると兵士になった。あるとき、ふとしたことで法を犯してしまい、斬罪に処せられることになった。隊長は張献忠の容貌を一瞥して奇異に思い、上司に彼を赦してやるよう進言した。上司はその言を容れ、張献忠は釈放された。
張献忠は飢えに苦しんだ。あるとき盗みをはたこうと家の屋根に登ったところ、夜空に神が鞭を持って現われた。張献忠は神を仰ぎ恐れ懼いた。神は鞭を振り上げると「とっとと立ち去れ。貴様が上帝より百姓を召し上げるために下界にくだされた者でなければ、撃ち殺してくれるところだぞ」と叱咤した。張献忠は転げ落ちるように屋根からおりると「おれが人を殺すのは天命だ」と心に刻み逃げ去った。
張献忠は米脂縣で兵を挙げたが、官軍に敗れ、山中深くに逃げこんだ。飢えに苦しんだ張献忠は、近くの寺に金や米がたくさんあると聞き、略奪に行った。寺の坊主は拳術をよくしていたが、「我々が応戦して奴を打ち負かしたら、奴は終生我々を恨むだろう。ここは禍を他人に転嫁した方がよい」と話し合い、学生の頭巾をつけて張献忠と戦った。張献忠は散々に打ち負かされ手下の多くが死んだ。これ以来、張献忠は学生や官僚に消しがたい怨みを抱いた。
張献忠が荊州を破ったとき、ある妓女が張献忠に召し出された。彼女はおのれの技芸のたけを尽して一心に機嫌をとって使えたので、張献忠はすっかり気に入り、誰よりもまして寵愛した。張献忠は毎晩、寝る前に必ず酒を浴びるほど飲んだが、ある夜、枕席にはべった妓女は毒を盛った酒を杯に満々とついで彼に差出した。張献忠はたわむれ、彼女の頸に手をかけながら「お前が先に飲め」といった。彼女は断ったが、とうとう断り切れず、一息に飲んで倒れた。彼は初めて気がつき、彼女の骸をずたずたに引き裂かせた。
張献忠は友達付き合いが大好きで、知人に会うと、徹夜して飲み、一行疲れる様子がなかった。そして帰るときは土産物をたくさん持たせて返した。ところが予め手下に命じて途中で待ち伏せ、その首を斬って持ち帰らせ、長持に入れておき、移動するときには車に積んで持って行った。そして陣中で酒の相手がなくて寂しいときは、長持を開かせ、「さあさあ、いらっしゃい」といいながら首を取りだして席上にずらりと並べ、杯を持って酌をして回り、生ける人に対するように楽しく語りかけ、これを「聚首歡宴」と呼んだ。
張献忠は蜀に入ると、兵を四方に派遣して殺し回らせた。「蜀の人間はまだ死に尽していないのか。おれが手に入れたのだから、おれが滅ぼしてしまうのだ。ただの一人でも他人のために残しておきはせぬぞ」と言い、人を殺した数によって兵の階級を上げた。ある一兵卒は一日に数百人を殺したというので、一足飛びに都督に抜擢された。
張献忠の軍では、人の手を斬り落とすとき、男は左、女は右と定められていた。もし間違えて差出すと両方とも斬られた。男の手足二百対を得た者には武官を授けたが、女の場合はその倍が必要で、子供の手足は数に入れられなかった。幼児は道端に捨てて馬蹄に踏みにじらせるか、空に投げ上げて落ちてくるところを刀で突き刺して殺した。
張献忠の軍では人の殺しかたに様々な名前があった。
「匏奴」とは手足を斬り落とす方法である。
「邊地」とは背筋で真っ二つに斬り離す方法である。
「雪鰍」とは空中で背中を槍で突き通す方法である。
「貫戲」とは子供たちを火の城で囲んで炙り殺す方法である。
ほかにアキレス腱を抜いたり、女の足を斬ったり、人の肝を搗き砕いて馬の餌にしたり、人の皮を剥ぎ取って大通りに貼り出したりした。
張献忠の軍では、人の皮を剥ぐときは頭から尻まで一直線に裂き、鳥が翼を広げたような格好になるよう前に広げた。生きながら皮を剥ぐ方法を編み出し、もし皮を剥ぎ終えぬうちに死んだ場合は刑手が死刑となった。ある人は皮を剥がれ、内臓を抉り出して代わりに藁を詰め、屍に衣冠を着けて曝された。またある人は皮を剝がれ、その皮は太鼓に張られた。それを城門に掛けて、出入りする者に叩かせた。
張献忠はついに蜀王を捕えた。張献忠が刀を振りあげ王を殺そうとしたとき、空に雲もないのに雷鳴が轟いた。張献忠は「貴様は人を殺すために俺様を下界にくだしたくせに、雷で嚇かすとはなにごとだ!」と怒り、空に向けて大砲を三発打ちあげた。そして王に向きなおると「もし、もう一度雷が鳴ったらお前を見逃してやろう」と笑ったが、二度と雷は鳴らず、王は殺された。王は死ぬとき、ゆらゆらと立ちのぼる白い霧の中に消えた。
張献忠はある夜、何もすることがなかった。彼はしばらく不思議げに首を傾げていたが、突然激昂し「今夜は誰も殺すべき奴はおらんのか!」と吼えた。そして自分の妻妾数十人を殺すよう命じ、たったひとりの子までも殺してしまった。翌朝、彼が妻子を呼び寄せようとしたので、側近が昨晩のことを話したところ、張献忠は「なぜ反対しなかった!」と怒り、今度は側近を皆殺しにした。
張献忠は学生を集め、縦横各一丈の新しい黄旗を出して、「帥」という字を大きく書くよう命じた。その大きさは一斗桝くらいで、それも一筆で書かねばならなかった。みごとに書けたものは殺さぬと言うのであった。あるものは、草を縛って作った筆を大甕に入れた墨汁の中に三日間漬けたのち、取り出して一気呵成に書きあげたが、髪の毛一筋のかすれもなかった。張献忠は、つくづくと眺めて、「大した男だ、後日、わしの命を狙うものがあるとすれば、必ずやお前だろう」といい、それを祭旗に用いることとした。
張献忠は投降した官吏三百人を殺したが、ある人があまりにひどすぎると言った。張献忠は「文官のなり手はいくらでもいる」といって、朝見の際、官吏が平伏しているところへ、数十頭の猛犬を呼び入れ、殿を下りて、犬が匂いをかいだ者を引きだして斬り捨て、これを名づけて「天殺」といった。
張献忠は科挙を行うと称して、試験場門前の左右に、地面より四尺の高さに長い縄を張り、姓名を呼び上げて並ばせた。そして、背丈が縄を越えた者は全て殺した。殺された者は一万人に及び、残された筆や硯は山のように積まれた。幼くて縄に届かなかったため殺されるのを免れたのは二人だけだった。
張献忠は科挙を行うと称して、学生ひとりひとりに銀貨を1枚あたえて頭上に頂かせ、東門から入って西門より出るところで首を斬り、銀貨を取り戻した。そして「首を売りたいのかい。貴様を殺すのもやっぱりおれだぞ」と言って大笑いした。
張献忠は科挙を行い、百二十人の進士を採った。首席合格者は身の丈七尺、弓と馬が頗る上手で堂々たる風采の偉丈夫であった。部下は上奏文を奉り「これは陛下の覇業を助けんと天が賢者を下したものでございます」と祝賀した。張献忠も彼を大いに気に入り、美女十人、豪壮な邸宅や下僕を与え大いに歓待したが、あまりのことに「俺はあいつが可愛くてたまらん。だがあいつの顔を見ると、可愛くて可愛くてどうにもやりきれん。お前たち、今すぐあいつを片づけて二度と俺の前に来ないようにしてくれ」といった。部下どもは勇躍して彼を縛り上げて殺し、家族を皆殺しにすると、下賜された美女・下僕もひとり残らず斬り殺してしまった。
張献忠はあるとき武官登用試験を実施した。民間で馬を養うことは禁止されていたが、集まった受験生を馬場に集合させると、一番兇猛な軍馬ばかり千頭あまりを引きだして騎乗させた。そして彼等が馬にまたがるや、兵士達がどっとはやしたて、大砲を撃ち、銅鑼太鼓を打ち鳴らしたので、馬は狂奔して乗り手を振り落とした上、泥となるまで踏みにじった。これを見て張献忠は手を打って大笑いした。
張献忠はあるとき医者たちを集めて針術の試験をした。太医院に古くから傳わる銅人に紙をかぶせて穴を隠し、一針でも刺し違えたときはその場で殺したので、医者は忽ち死に絶えた。
張献忠が攻めてくると聞いた城では人々がこぞって逃げ出したが、ひとりの老人は家に残った。杖にすがり張献忠に会うと、日ごろ貧乏で困っている様子を縷々と訴えたすえ、主人としてちゃんとおもてなしすることのできぬのは申訳ないといって詫びた。張献忠は「そんなに苦しいなら何もこの世に生きていることもあるまい」と大笑いし、老人を殺した。
張献忠が攻めてくると聞いた城では人々がこぞって逃げ出したが、ひとりの老人は家に残った。「みな出ていってしまったら、この家の道具類は誰が番をするのだ。人に盗まれてもよいのか。おまえたちは行くがよい。わしが残って番をしてやる」間もなく張献忠の軍が大挙来襲し、家を焼き払って老人を殺してしまった。
張献忠が攻めてくると聞いた城では人々がこぞって逃げ出したが、逃げ切れぬと悟った人々は酒屋に殺到した。人々はどろどろに酔い、そして張献忠の前に首を差しだした。酒屋は千金の儲けを得て大いにほくほくていたが、やがてその顔のまま首が地に転がることになった。
張献忠が保寧を攻めたとき、夜間の巡視に出たところ、ひとりの真黒い巨人が蛇矛を持って城壁に腰をおろし、足を嘉陵江に浸しているのを見て、驚きのあまり声も出せなかった。このようなことが三夜つづいた。張献忠は人に聞いて、それが張飛が現われたものと知り、遙かな中空を望んでその霊を祭ったのち城攻めにかかったところ、事なく陥れることができた。
張献忠が羅江縣の落鳳坡を攻めたとき、龐統を祀った祠を壊した。その夜、龐統が夢枕に立って激しく責めたてたので、彼はひどく恐れ、改めて建て直した。その壮麗さはもとの数倍であった。
張献忠がある城を攻めたとき、僧が民衆のために命乞いをした。すると張献忠は犬と豚の肉をつきつけて、「やい坊主、これを食ったら、お前の言うとおりにしてやろう」と言った。僧は「百万の生霊のためとあらば、如来の戒ひとつ破るくらいなんでもありません」と言って何片かを食ったので、彼もついにこれを許した。
張献忠が梓潼を攻めたとき、夜の夢に従兄弟と名乗る人が名刺を出して面会を求めた。そして住民を殺さぬよう求めた。朝になって張献忠がこのことを人に話すと、「それは文昌帝君でしょう」と言った。そこで張献忠は「じゃ、俺たちは一家の兄弟というわけだな。それなら殺すに忍びぬわい」といい、梓潼の民は殺されることはなかった。
張献忠は文昌帝君を祭ることにしたが、知識人が作る祭文は張献忠には意味が分からなかった。そのため多くの士人が殺された。張献忠はついに「よし、おれが自分で作る。お前たちは書き取れ」と大声で叫び、「おれさまの姓は張だし、お前の姓も張だ。なんでおれさまを嚇かすんだ。俺とお前と親戚づきあいをしようじゃないか。尚くは享けよ」人々はその無学を笑った。
張献忠は部下があまりに多すぎるのが気に入らなかった。「おれが旗挙げしたとき、ついてきた者はわずか五百人であったが、向かうところ敵なしというありさまだった。しかるに近頃は増える一方だ。そういう連中は欲に目がくらみ二心を抱く奴がいる。だから旗挙げ以来の古強者だけを手元に残そうと思う。家族の多い者も除いてしまう。こうすれば、おたがいに身軽になって、向かうところ敵なしだ」と言い部下も殺して回った。陣屋内で私語をしたり、些細なことであれ過ちを犯した者は見つけ次第処刑された。その際は関係者、家族まで連座して殺された。人々は恐れおののいて、一言も口をきく者がいなくなった。
張献忠は子供を使って夜の路地裏を見回りさせ、陰口が聞こえると門に白堊でしるしをつけさせた。朝になるとその家の者を全部捉えて殺した。あるとき、スパイが「張家は長く、李家は短し」と歌をうたった者を引っ張ってきたことがあった。張献忠は「これは私が李自成に勝つ前兆だ」と笑い、その者を放してやった。
張献忠が蜀を支配していたころ、飢饉が続き、人々はたがいに食い合った。行き倒れのしかばねは、あとかたもないまで食い尽くされた。家から一里先の道端に餓死者が倒れているというので、誰彼が、夜になったらそれを盗んでこようと相談した。ところがいよいよそこに行ってみたところ、首がひとつ残っているきりで、とっくに誰かが持ち去ったあとであった。
張献忠が蜀を支配していたころ、飢饉が続き、人々はたがいに食い合った。屍さえ手に入れられなくなると、親子、兄弟、夫婦がたがいに殺しあうまでになった。死体は日に乾して干し肉にされた。老人は饒把火(松明よりは食うところがある)、婦女や少年は下羹羊(スープ用)、子供は和骨爛(骨まで煮て食える)と呼ばれた。
張献忠が蜀を支配していたころ、飢饉が続き、人々はたがいに食い合った。生き延びた老人の中には目が蝋のように黄色い者がいた。それは例外なく人の肝を食った者であった。
張献忠が蜀を支配していたころ、ある家の庭に三本のすももの木があった。その家の主人はすももが熟してもわざとちぎらずにおいて、通りがかりの人が盗むように仕向けた。そして盗むところを捕えてはその罪を責め、殺して食った。
張献忠が蜀を支配していたころ、ある人が山中の茅葺き小屋の前を通りがかった。見ると煙突からさかんに煙が立ちのぼっているので、どうやら人が住んでいるらしいと思い、中に入り、釜の中に煮ているのを見たところが、みんなそれが人の手掌や足だったので、驚きのあまり声も出なかった。幸いその時家の者が外に出ていていなかったから良かったが、さもなくば命が無いところであった。
張献忠が蜀を支配していたころ、さまざまな病が流行した。大頭瘟とは頭が真っ赤に腫れ上がり、一斗桝ほどの大きさになった。馬眼睛というのは両眼が大きく黄色に腫れ上がり、にゅうぅと飛び出した。馬蹄瘟というのは、膝からスネまで全部真っ黒に腫れ上がり、馬の蹄のようになった。この三つの病にかかったものは、絶対に助からなかった。
張献忠が蜀を支配していたころ、ある人は賊を避けて深山に逃れ、、草を身に纏い木を食って暮らした。長い間そうしているうち、姿形があたかも鹿のようになった。のちに官軍の兵士を見かけたが、また賊が襲ってきたのだと思い、びっくりしてどんどん山へ逃げ登ったが、それはまるで飛ぶような速さで、やがて手をついて四本足で駆けていった。彼を見た者によると、その身体はすっかり毛で覆われていたという。
張献忠の軍が通過したとき、ある人は深い竹藪に逃げこんだ。夜になると、山の向こうから真っ黒な巨人があらわれ、死体の中に分け入り、その首を拾い上げ、両手で引き裂いて、片端から脳髄を啜って帰って行った。朝になってみると、脳髄の残っている頭はひとつも無かった。おそらく夜叉のたぐいであったのだろう。
張献忠が瘧を病んだとき、天に向かって「この病気が治ったら、天に届く蝋燭を二本だけ献じましょう」と祈った。張献忠は病気が治って起き上がると、女の纏足した足を斬って二つの山に積み上げさせた。あるとき足首の山の下で愛妾と酒を酌み交わしていたが、ふと山を振り仰いで「足がもうひとつあったら、尖った山頂ができるのだがな」といった。そこでその妾が自分お足を差し上げて冗談に「これでどうでしょう」というと、張献忠は「よかろう」といって、即座に切り落とさせた。この足首の山に脂を注いで火をつけると、臭気は天に達した。張献忠はそれを見て狂喜した。
張献忠に清軍が目の前に迫っていると報告する者があった。彼はそんなはずはないとして、その者を斬り「やつらはいい加減なことをいって甘い汁にありつこうとしたのだ」と言った。間もなくまた知らせに来た者があったので、これも斬った。三度目に知らせた者もまた斬った。清軍は張献忠の油断に乗じて急襲し、その矢は張献忠の喉に突き立った。彼は矢を引き抜いてつくづく眺め「なるほど清軍だな」と言うと、薪の下に隠れたが、引き摺り出されて八つ裂きにされた。
張献忠が死んだとみるや、民衆が群れ集まりこもごも死体に斬りつけた。人々が張献忠の屍を切り開いてみたところ、心臓は墨のように黒かった。また心臓は扁平で、肝臓はなかった。死体は骨も肉も見分けもつかぬまでにぐたぐたになった。
張献忠の屍を埋めた場所には棘のある草が生い茂り、あやまってそれに触れると、大きなできものができた。また、いつも黒い虎が墓を守って人を食ったので、誰も近寄ろうとはしなかった。



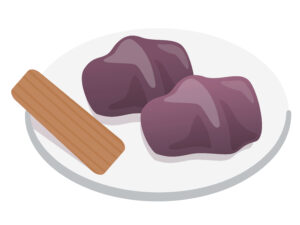



※コメントは最大500文字、5回まで送信できます