子どものころ、おやつにときどき干柿や干し芋が出た。
いつしか私は白い粉をたくさん吹いたものを自然と選ぶようになったのだが、長いことそれを不思議に思っていた。経験的にその方が美味いのである。
あるとき「あの粉は後づけされた甘味料で、それが美味いのだろう」と思い、干柿を互いにこすり合わせて粉を集め、それを舐めてみたことがあった。ところが案に外れ、ほのかに甘いものの、とりたてて何か言うような味はせず、しばし首をかしげたのであった。
あとになって調べてみると、あの白い粉は果糖とブドウ糖が表面に析出したものであるらしい。柿の糖含有率は約20%で、その大半がショ糖、果糖、ブドウ糖である。果肉にはスクラーゼがあるため、これが乾燥中にショ糖をブドウ糖と果糖に分解し、干柿に含まれるの糖は果糖とブドウ糖ということになる。したがって、糖を多く含む柿はたくさんの粉を吹く、故に美味、という理屈なのだろう。
粉の味がしなかったのは、少量であったせいかもしれず、もしかすると粉は甘味の薄いブドウ糖の方が多いのかもしれない。果糖は低温でその甘さが強くなるから、干柿も常温より冷やした方が美味いのだろうか。
『本草綱目』を開くと、この粉は「柿霜」と書かれている。むかしは砂糖の代用や鎮咳剤として薬用にも用いられたらしい。確か徳島藩は柿霜を幕府に献上していたはずである。
ふと思ったが、「粉を吹く」というのは英語でなんと表現すればよいのだろうか。一応 mealy という単語があるようだが、実用的には “a dried persimmon with white deposits (on its skin)” くらいだろうか。ただ “white deposits” だと字面がなんか病的に見えるので、普通に “sugar powder” とした方が通りがいいかもしれない。
魯迅の日記を読んでいると、ときどき「柿霜糖」というお菓子が出てくる。
密斯高是很少來的客人,有點難於執行花生政策。恰巧又沒有別的點心,只好獻出柿霜糖去了。這是遠道攜來的名糖,當然可以見得鄭重。
『馬上日記』1926年7月8日
我想,這糖不大普通,應該先說明來源和功用。但是,密斯高卻已經一目了然了。她說:這是出在河南汜水縣的;用柿霜做成。顏色最好是深黃;倘是淡黃,那便不是純柿霜。這很涼,如果嘴角這些地方生瘡的時候,便含著,使它漸漸從嘴角流出,瘡就好了。
她比我耳食所得的知道得更清楚,我只好不作聲,而且這時才記起她是河南人。請河南人吃幾片柿霜糖,正如請我喝一小杯黃酒一樣,真可謂「其愚不可及也」。(中略)但密斯高居然吃了一片,也許是聊以敷衍主人的面子的。
ミス高という珍しい客に大切な「柿霜糖」をおやつに出したときのことである。貴重な品だから、と魯迅が由来やら効能やら説明しようとしたが、先方とっくに「これは柿霜糖ね」と承知であったという。それも道理、彼女は河南の人であった。柿霜糖は河南汜水縣の名産で、柿霜からつくられるお菓子らしい。最上級品は濃い黄色であるが、魯迅の出したものは薄い黄色であった。これは混ぜ物がしてあるためだと彼女は言う。
この「柿霜糖」だが、「口角が荒れているときにこれを食べれば、口からすっと抜けるような清涼を感じ、あっというまに治ってしまうという」と書かれているように、おそらく甘味の強すぎない果糖、ブドウ糖が主体のお菓子なのだろう。また色からするとおそらく果肉も含まれているにちがいない。そういえば、周作人は日本留学時代に大垣の柿羊羹を食べていたく気に入ったらしい。この兄弟はもしかすると柿が好きなのだろうか。神田にゆくたびに買っていたとのことだが、いつしか店頭に並ばなくなったらしく、三十年以上たってからもそのことを惜しむ文を残している。閑話休題。
* 木山英雄編訳『日本談義集』平凡社、2002年3月
さて「其愚不可及也」*と魯迅はぼやいているが、確かに「東京ではこれが美味しいんですよ」と博多っ子に「銘菓ひよ子」を出すようなものである。そういえば、私も静岡に勤めていたころ、京都土産に茶を職場に持って行ったことがあった。渡すときになって相手の実家が茶農家であることを思い出し、「アッ」と手を引っようとしたが時すでに遅かった。相手は「ほほう京都のお茶ですか。たまにはいいですね」とニヤニヤしておしまいにしてくれたので助かったのだが、まさに「その愚や及ぶべからず」であった。
* 『論語』公冶長第五
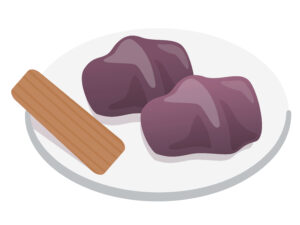




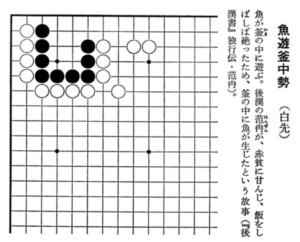
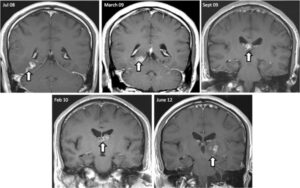

※コメントは最大500文字、5回まで送信できます