旅人なればこそ
小柴がくれに茜さす
いとしき嫁菜つくつくし
摘まんとしつつ
吐息つく
まだ春浅くして
あたま哀しきつくつくし
指はいためど 一心に土を掘る
本棚から詩集をとりあげて眺めていたら、祖父母の家でつくしを食べたことを思い出した。
私がこどものころ、祖父母の家は横浜の郊外にあった。当時は住宅造成途中で放置された草っ原や広い公園があちこちに残っており、春に訪れた時は必ず土筆採りに出かけたものである。
つくしを見つけても、道路脇のものは取ってはいけないと言われていた。なぜかというと、車の排気や犬のションベンが染みついて妙なにおいがするからである。だから私は草の生えていそうな高台を探すようにしていた。
ちくちくちくちく採って家に戻り、それらをザルにあけ、チラシをひいたテーブルの上で袴を取るところまでが私の仕事である。「よう採ってきたね」と祖母に上納される頃には爪のなかにたっぷりと土が詰まって真っ黒になっていたものだった。

私が食べたことのあるつくし料理はおひたしと卵とじである。卵とじが私は大好きだった。袴をとった土筆をザルでよく洗い、熱湯で茹でこぼしたあと、みりん、しょうゆ、砂糖、だし粉、水少々と一緒に火にかけ、沸騰して水気が飛んだら溶き卵でとじてやるのである。
戦前の料理本なんかを眺めていると、粕漬けや辛子和えなんかもあったそうである。
個人的には天ぷらなぞ良いのではないかと思うが、なかなか機会がなくそのままになっている。想像するに、淡泊でほのかに甘く、きっと塩が合うだろう。イモやカボチャのような食べでのあるものなら天つゆの方が良いのだろうが、こういう繊細なものはやはり塩がいい気がする。
春にあまりいい想い出もないが、この春の使者は失意の人を慰めるものらしい。『病牀苦語』のなかで子規もまたつくしに心を癒やされている。
根岸に越してきた碧梧桐の一家が土筆採りに行くことになった時、看病に疲れた妹が誘われたのを、子規は「予まで嬉しい心持がした」と喜んでいる。一行は田端から汽車に乗って、飛鳥山の桜を一見し、それから歩いて赤羽まで行ったらしい。
そうして採ってこられた風呂敷いっぱいの土筆は彼の目の前に出し広げられた。
袴をむきながらしきりに独り言を言う妹の姿を眺めながら「何となく愉快そうな調子で居る彼*を見ると、平生の不愛嬌には似もつかぬ如何にも嬉しそうに見えるので、それを病床から見て居る予は更に嬉しく感じた」と子規は書いている。
* 妹のこと。明治の頃は女性も「彼」と呼んでいたのである。
家を出でゝ土筆摘むのも何年目
病牀を三里離れて土筆取
にぎやかな春の陽気をまとい土筆の袴をむしる妹と、それを死の床から眺める子規の姿を思い浮かべると、明るい陽がその陰を濃くするように私には思われてならない。
だから春は嫌いなのさ。



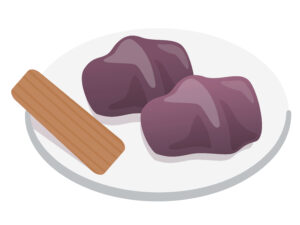



※コメントは最大500文字、5回まで送信できます