亡くなった祖父の書架を整理していたとき、紙魚を見たことがあった。あれはたしかアンドレ・モーロワの『英國史』で、今は珍しいフランス装の本だった。
紅箋白紙兩三束 紅箋白紙兩三束
半是君詩半是書 半は是れ君が詩、半は是れ書
經年不展緣身病 年を經て展べざりしは身の病めるに緣る
今日開看生蠹魚 今日開き看れば蠹魚を生ぜり
赤い紙と白い紙の束がふたつみっつ
君がくれた詩や手紙だね
しばらく開いてなかったけど、僕も病気で臥せっていたんだ
今日久しぶりに広げてみたらさ、紙魚がいたよ
持ち主に忘れられた書には彼らがあらわれるのだろうか――そんなことをぼんやり考えているうち、紙魚は銀閃を翻して紙間にその姿を隠してしまった。本をパラパラとめくって行衛を探したが彼はどこかに消えてしまっていた。もしかするとまだ切り開かれていないページにでも行ってしまったのかもしれない。
むかし、紙魚は書物の「神仙」二字を三回食べると身体が五色に輝き、脉望になると言われた。そして人が脉望を呑めば仙人になれるとも。
唐のころ、張易之の子は「神仙」と書いた紙をたくさん甕の中に詰め、そこに紙魚を放した。しばらくたってもう脉望になった頃合いであろう、と彼は甕の中の紙魚を呑んだが、仙人になることはできず、かえって気の病になってしまったという。
『本草綱目』卷四十一「唐張易之之子乃多書神仙字碎剪置瓶中取魚投之冀其蠧食而不能得遂致心疾」
『英國史』に「神仙」の字はあるまいが、祖父のかわりに続きを読んでくれたであろうあの紙魚は今どこで何をしているのだろう、と思うことがある。



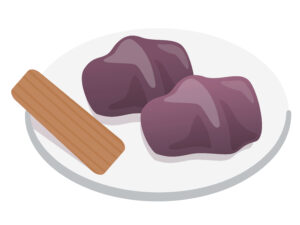



※コメントは最大500文字、5回まで送信できます