日日利用するオンライン辞書に JapanKnowledge というサイトがある。
私はいつも公式のアイコンに従ってJKと略しているのだが、どうも一般にはJKというと別のものを指すらしい。あるとき「JKのサブスクリプションはいいよ」と言ったところ友人に妙な誤解をされたことがある。
「JKに課金……?」
「うん。年に2万ちょいじゃなかったかな」
「2万……年に?」
今日も「quantitation と quantification の違いって何だろう」と辞書を引くためにサイトを訪れたのだが(結局よくわからなかった)、トップページに載っていたダンゴの写真がおいしそうであったので思わずクリックしてしまった。飛んだ先はダンゴとは関係ないコラムで、なんとなくそのまま読んだのだが、内容について若干思うところがあったので記しておく。
題は「『爪痕を残す』は、何を残すのか?」で、要約すると以下のごとくである。
うーん。まあ結論はその通りだと思うのだが、どうも話があべこべである。そもそも「爪痕」は芥川のように「ある領域において成し遂げた成果」「ある分野に残した足跡」の意で用いるのが本来の用法であって、「災害や戦禍の被害や影響」のような否定的な意味合いで用いるのはむしろ後づけなのである。
明治大正期の「爪痕」の用例を挙げてみよう。むろん物理的に爪で引っ掻いた痕の意ではなく、比喩的に用いられているものに限る。
大丈夫一たび此地球上に生る必ず之れに一大爪痕を印す可きのみと
中江篤介(兆民)『一年有半』博文館(1901年)余は俳句を解せぬ者なるを以て正面の子を見るの資格なきものなれども肺部の腐蝕は云ふ迄もなく遂には四肢の骨々も皆腐れて齒に及び其腐汁滴たる身体の内に尚此絶世の精氣を寓せしめて天下に多大の爪痕を印し得たる子が不思議の力には只々感歎の外あらざるなり
正岡子規著、小谷保太郎編『子規随筆』吉川弘文館(1902年)諸君はまこと叙事詩壇の陳勝呉廣として、明治文學史上、確かにその爪痕を印したるものといふべし。
小嶋烏水、與謝野鐵幹「文藝雜爼」/「明星」1902年4号月旦子曰く、德川慶喜公は日本に於ける歷史的人物として最も偉大なるものゝ一人なり。是其の人格の偉大なるに非ずして、其の行藏の歷史上の大事實と關聯して、千歳磨滅す可からざる爪痕を留めたればなり。
『春汀全集3』博文館(1909年)而して東肥洋行は一月二日忽ち火を失し、邦商發展の一爪痕さへ既に烏有に歸し去りぬ。
山田勝治『飲江三種』江陵義塾(1917年)自分は此の新らしきウイルソン氏の家の中を見廻つて、是が世界人文史上に一大爪痕をとゞめた偉人の最後の住家であるかと侘立願望、低徊之を久しうした。
いずれもふりがななし
鶴見祐輔『歐米名士の印象』實業之日本社(1921年)
一覧にすると瞭然だが、いずれも「時代・歴史・分野にその蹤跡を留める」の意で用いられていることがわかる。災害や戦禍に対して用いられたものは見られない。
私がこのコラムを不審に思うのは、芥川の用例を挙げておきながら、「印象づける」の意になぜ「爪痕」という言葉を用いるのか、という点について全く触れていない点である。まさか不思議に思わなかったわけもあるまいが、私が竊かに危惧するのは、もしかすると著者は「爪」を人間の爪と思っているのかもしれない、ということである。
そんな馬鹿なことはあるまいが、いちいち指摘しておくと「爪痕」は「鴻爪」のことである。蘇軾の七絶「和子由澠池懷舊」(子由の「澠池懷舊」に和す)を知らないと言われればああそうですか、しかたないですね、と言わざるをえないが、「雪泥鴻爪」あるいは「鴻爪春泥」を聞いたことがないと言われるとこれはもうどうすればよいかわからない。
人生到處知何似 人生 到る處 知んぬ何にか似たる
應似飛鴻踏雪泥 應に似たるべし 飛鴻の雪泥を踏むに
泥上偶然留指爪 泥上 偶然として 指爪を留むるも
鴻飛那復計東西 鴻 飛びて 那ぞ復た東西を計らん
老僧已死成新塔 老僧は已に死して新塔を成し
壞壁無由見舊題 壞壁は舊題を見るに由無し
往日崎嶇還記否 往日の崎嶇 還お記するや否や
路長人困蹇驢嘶 路長く 人困じて 蹇驢嘶きしを
人の一生というものはいったい何に似ているのだろうか。
きっと、空を舞う鴻おおとりが雪の上に舞い降り、偶然そこに爪のあとを残すようなものだろう。
鴻が飛んで行ってしまえば、東に行ったのか西に行ったのか、それはもうわからない。
あの老僧も亡くなり、今や新しい石塔の中の人となった。
私たちが字を書きつけた寺の壁も崩れ落ちてしまった。
あの日の険しい山道をお前(弟の蘇鉄)はまだ覚えているだろうか。
道は長く、人は疲れ果て、脚を引きずる驢馬が哀しげにいなないたあの日のことを。
「雪泥鴻爪」は蘇軾のなかでも有名なもので、我が国の漢詩人にもよく知られていた。たとえば森春濤の漢詩に「留看飛鴻舊爪痕」の句があり、頼山陽の「僦居五首」にも「何圖鴻爪跡」とある。
頼山陽が広島から来た加藤王香を嵐山に案内したとき、王香の所持していた瓢を誤って落とし、瓢の腹に傷をつけてしまったことがあった。その時山陽が言ったのが
庚庚横理君宜記、亦是春鴻舊爪痕
である。
「庚庚横理」は漢の代王が陳平らの招きに応じて皇帝になるべきかどうか迷ったとき、占いをしたところ「大橫庚庚,余為天王,夏啓以光。」と出た故事による(『史記』孝文本紀)。前半「大橫庚庚」については『史記索隠』に「荀悅云う、大橫は龜兆の橫理(横にはいった筋)なり、と。按ずるに庚庚は更更のごときなり」とある。後半は「私は天下の主(皇帝)となって夏の啓のように父(禹)の業を継いで光をもたらすであろう」の意。要するに、山陽は瓢についてしまった横一文字の傷を亀卜になぞらえて「これは吉兆だよ、君覚えておきたまえ」と言っているのである。そして「亦是春鴻舊爪痕」は「それにこの傷は私と君が春に嵐山に遊んだことを思い出す縁にもなるよ」くらいに解釈できる。人の愛瓢に傷をつけて言うことではないような気もするが、まあそういうことを言える仲であったのだろう。
明治に入ると、たとえば前島密は自叙傳を「鴻爪痕」と題し半生を語っている。自序の冒頭に以下のようにある。
余が自ら鴻爪と號せるは、雪泥に印せる爪痕の、爭でか久しく存すべきと觀念せるに依るなり。
市野彌三郎遍『鴻爪痕』前島彌、1920年
また、ロシアで客死した大庭柯公の追悼文に「鵠鵬の爪痕」というものがある。 鵠は鴻と並んでおおとりに喩えられる。鵬もおおとり。
大庭君は、新聞記者界の鵠鵬である。或時は「毎日」に、或時は「朝日」に、而して或時は「讀賣」にその爪痕を印し、遂にロシアの天地に翺翔してその終るところを知らぬ。嗚呼その歸來する日はいづれぞや。
『柯公追悼文集』柯公全集刊行会、1925年、p120-123
もうひとつだけ例を挙げておこう。
前途春秋に富める我國現代の青年は先づ徐ろに功名心を養ひ多數を率ゐる少數の選民たらんことを期して人生飛鴻の雪上を歩するが如く須らく爪痕を留むることに勉めよ
大阪毎日新聞 1912年8月31日
時代を経るとともに人々の間から漢詩文の知識が喪われ、想像力は翼を喪った。その結果「爪痕」はただ爪を立てて何かに傷をつけるというだけの陰惨な、そして貧困なイメージしか残らなくなったのかもしれない。
――しかし、鴻とわかれた「爪痕」が今再び肯定的な文脈で用いられるようになろうとは、東西を計りがたいのはまた鴻だけではなかったということか。
後日追記:上のようなことを酒席で歳の離れた友人に愚痴混じりに話したところ、彼は「かつて爪印とか爪判というものもありましたよね。『爪痕』はその影響もあるのではありませんか」と指摘してくれた。あっ。たしかにそうかもしれない。爪印、爪判とは印鑑代わりに爪痕を用いたもので、親指の先に印肉をつけて押捺し、ハンコのかわりにした。印肉をつけず、ただ爪の圧迫痕のみをつけた場合も多いらしい。


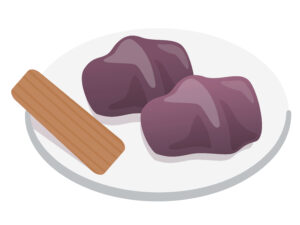




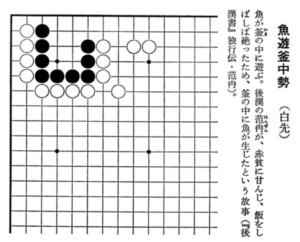
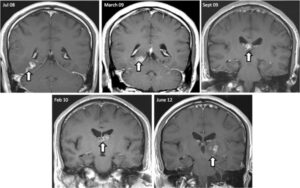
※コメントは最大500文字、5回まで送信できます